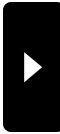2012年06月12日
サッカー 日本‐ヨルダン戦について ヨルダンより報告!
みなさん、こんにちは。
すっかり梅雨の季節となりましたね
雨の日、どんな過ごし方をされていますか?
さて、今日は、ヨルダンで青年海外協力隊・幼児教育
で活動されている江口隊員より、
なんと6月8日に行われた
日本 VS ヨルダン戦
について報告が参りました~






圧勝でしたね
あの日以来、会う人会う人に「6-0」と言われます
(悪気があるわけではなく、冗談めかして)
「3月にあるヨルダンー日本戦ではヨルダンが圧勝だ 」
」
というおっちゃんや
「本田めーーー。でも俺の車はホンダなんだ」
というおっちゃんやらいろいろいておもしろいです

 ヨルダンのサッカー事情
ヨルダンのサッカー事情

サッカーはみんな好きだけど、
基本的にはバルサかレアルかどっちが好きか?ってはなしをします。
国内リーグもまぁまぁ人気はあるけど、人気のあるチームは2~3チームでそれ以外はほとんどファンはいません。
(ちなみに人気の2チームは元祖ヨルダン人対パレスチナ人って構図)
ヨルダン代表もそれなりに人気があります。

(この写真は、6月3日に行われたイラク対ヨルダン戦。
ヨルダンサイドの観客の様子です)

 6月8日の当日の様子
6月8日の当日の様子

私は日本人10名くらい集まって、ホテルで鑑賞していたのですが、
当日、たくさんの人が集まる屋外カフェでヨルダン人の中にまじって
鑑賞していた協力隊がおりまして、彼に様子をきいてみました
「 数日前から日本戦だと言われ、当日は金曜礼拝の後、
喫茶店に人が集まりだす。
ちょうどそのあたりの時間にキックオフ。
アカバの屋外カフェには50人くらい。(うち日本人2人)
ずっと押されてるから結構しずかで、1点2点と入ってさらに静かで・・・。
前半30分ごろ、ヨルダン14番が退場になったあたりから人が帰りだし・・・
点が入るたびに人がいなくなり・・・
もう完全にあきらめムードで日本に点が入ると喜んでくれる。
終了時には5人くらい。」
こんな様子だったみたいです
ちなみに私は日本人だけで鑑賞していたのですが、
あまりに点差が開きすぎてきて、
だんだんヨルダン側の立場になりヨルダンチームがかわいそうになったり、
ヨルダン人の気持ちを代弁したりそんな声がみんなの中から聞こえている状態でした。

(日本対ヨルダン戦を協力隊の仲間たちと観賞。勝利後にパチリ
ヤッター )
)
それから、ヨルダン人と2年間すごしてきて、
ヨルダン人の顔には見慣れているのですが、
あんなにたくさんの日本人をテレビで見たのは久しぶりだったので、
みんなで
「うわーーーー。すごいわーー。日本人がたくさん!!めっちゃ違和感やねー。」
とちょっとなつかしい気持ちで観客席をみていました



いかがでしたか?
サッカーから、ヨルダン人のおおらかさが伝わってきましたね。
また、2年間異国の地で過ごす、日本人の気持ちもよくわかります!
さて、本日は、オーストラリア戦
ただ、オーストラリアに協力隊は派遣されておりませんので、
次回の報告はありません
すっかり梅雨の季節となりましたね

雨の日、どんな過ごし方をされていますか?
さて、今日は、ヨルダンで青年海外協力隊・幼児教育
で活動されている江口隊員より、
なんと6月8日に行われた
日本 VS ヨルダン戦

について報告が参りました~







圧勝でしたね

あの日以来、会う人会う人に「6-0」と言われます

(悪気があるわけではなく、冗談めかして)
「3月にあるヨルダンー日本戦ではヨルダンが圧勝だ
 」
」というおっちゃんや
「本田めーーー。でも俺の車はホンダなんだ」
というおっちゃんやらいろいろいておもしろいです


 ヨルダンのサッカー事情
ヨルダンのサッカー事情

サッカーはみんな好きだけど、
基本的にはバルサかレアルかどっちが好きか?ってはなしをします。
国内リーグもまぁまぁ人気はあるけど、人気のあるチームは2~3チームでそれ以外はほとんどファンはいません。
(ちなみに人気の2チームは元祖ヨルダン人対パレスチナ人って構図)
ヨルダン代表もそれなりに人気があります。

(この写真は、6月3日に行われたイラク対ヨルダン戦。
ヨルダンサイドの観客の様子です)

 6月8日の当日の様子
6月8日の当日の様子

私は日本人10名くらい集まって、ホテルで鑑賞していたのですが、
当日、たくさんの人が集まる屋外カフェでヨルダン人の中にまじって
鑑賞していた協力隊がおりまして、彼に様子をきいてみました

「 数日前から日本戦だと言われ、当日は金曜礼拝の後、
喫茶店に人が集まりだす。
ちょうどそのあたりの時間にキックオフ。
アカバの屋外カフェには50人くらい。(うち日本人2人)
ずっと押されてるから結構しずかで、1点2点と入ってさらに静かで・・・。
前半30分ごろ、ヨルダン14番が退場になったあたりから人が帰りだし・・・
点が入るたびに人がいなくなり・・・
もう完全にあきらめムードで日本に点が入ると喜んでくれる。
終了時には5人くらい。」
こんな様子だったみたいです

ちなみに私は日本人だけで鑑賞していたのですが、
あまりに点差が開きすぎてきて、
だんだんヨルダン側の立場になりヨルダンチームがかわいそうになったり、
ヨルダン人の気持ちを代弁したりそんな声がみんなの中から聞こえている状態でした。

(日本対ヨルダン戦を協力隊の仲間たちと観賞。勝利後にパチリ

ヤッター
 )
)それから、ヨルダン人と2年間すごしてきて、
ヨルダン人の顔には見慣れているのですが、
あんなにたくさんの日本人をテレビで見たのは久しぶりだったので、
みんなで
「うわーーーー。すごいわーー。日本人がたくさん!!めっちゃ違和感やねー。」
とちょっとなつかしい気持ちで観客席をみていました




いかがでしたか?
サッカーから、ヨルダン人のおおらかさが伝わってきましたね。
また、2年間異国の地で過ごす、日本人の気持ちもよくわかります!
さて、本日は、オーストラリア戦

ただ、オーストラリアに協力隊は派遣されておりませんので、
次回の報告はありません

2012年04月27日
ブログの紹介です!
いよいよ明日からはGWですね
みなさんのGWの計画は?
さて、今回は、昨年6月より大洋州にあるミクロネシアで
水産物流通で活動されているシニア海外ボランティアの
松岡さんのブログをご紹介いたしますよ~

このブログは『JICA World Reporter』のブログとして公開されています

 http://worldreporter.jica.go.jp/
http://worldreporter.jica.go.jp/
『JICA World Reporter』とは?
アフリカ、中東、大洋州、中米、南米から
73名のJICAボランティアがブログで
派遣先の人、生活、文化、活動など身近なことを報告しています。
こちらが、松岡さんのブログ http://worldreporter.jica.go.jp/s23-1matsuoka/
http://worldreporter.jica.go.jp/s23-1matsuoka/
大洋州にあるミクロネシアの小さな島、ヤップの漁業公社に勤めながら、活動や周りの出来事を報告されています


 現在公開済みの内容は以下の通りです。
現在公開済みの内容は以下の通りです。
ブログ1(最初に出会ったのは)02.16.12
ブログ2(てんぷらを売るーその1)02.23.12
ブログ3(てんぷらを売るーその2)03.01.12
ブログ4(悪夢のような船酔いからの生還・その1)03.11.12
ブログ5(悪夢のような船酔いからの生還・その2)03.15.12
ブログ6(悪夢のような船酔いからの生還・その3)03.22.12
ブログ7(悪夢のような船酔いからの生還・その4)03.29.12
ブログ8(一家族6人の小さな島・その1)04.05.12
ブログ9(一家族6人の小さな島・その2)04.12.12
ブログ10(てんぷらを売る・悲哀)04.19.12
今後の公開予定ブログは次の通りです

原則毎週木曜日が公開日。
ブログ11(てんぷらを売る・試行錯誤)
ブログ12(てんぷらを売る・起死回生)
ブログ13(ヤップ島ツァー・マキ公学校)
ブログ14(ヤップ島ツァー・銀河)
ブログ15(てんぷらを売る・まだまだ、半眼)
ブログ16(てんぷらを売る・まだまだ、戸惑い)
ブログ17(てんぷらを売る・まだまだ、言い訳)
ブログ18(てんぷらを売る・まだまだ、課題)
ブログ19(不思議の島モンモン・そう簡単には行けません1)
ブログ20(不思議の島モンモン・そう簡単には行けません2)
ブログ21(不思議の島モンモン・いよいよ上陸)
ブログ22(不思議の島モンモン・後にして)
ブログ23(不思議の島モンモン・その答え?)
「一寸した切掛けで始めたてんぷらの製造販売、
今後どうなって行くか私にも見当が付きませんが、
たとえ頓挫してもありのまま率直に最後の結末まで
書こうと思っています。」とのこと。
「もう一つは離島の多いこの国、
その小さな島に世界の問題の集約された現実を見た思いもしています。
離島を訪ねるチャンスはそう無いのですが、
機会があれば出来るだけ迫りたいと思っています。」
シニア海外ボランティアの活動にご興味のある方は、
ぜひご覧になってみてください
 現在、シニア海外ボランティア募集中
現在、シニア海外ボランティア募集中
(4/1~5/14)です!
詳しくはコチラ http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html

みなさんのGWの計画は?
さて、今回は、昨年6月より大洋州にあるミクロネシアで
水産物流通で活動されているシニア海外ボランティアの
松岡さんのブログをご紹介いたしますよ~


このブログは『JICA World Reporter』のブログとして公開されています


 http://worldreporter.jica.go.jp/
http://worldreporter.jica.go.jp/『JICA World Reporter』とは?
アフリカ、中東、大洋州、中米、南米から
73名のJICAボランティアがブログで
派遣先の人、生活、文化、活動など身近なことを報告しています。
こちらが、松岡さんのブログ
 http://worldreporter.jica.go.jp/s23-1matsuoka/
http://worldreporter.jica.go.jp/s23-1matsuoka/大洋州にあるミクロネシアの小さな島、ヤップの漁業公社に勤めながら、活動や周りの出来事を報告されています



 現在公開済みの内容は以下の通りです。
現在公開済みの内容は以下の通りです。ブログ1(最初に出会ったのは)02.16.12
ブログ2(てんぷらを売るーその1)02.23.12
ブログ3(てんぷらを売るーその2)03.01.12
ブログ4(悪夢のような船酔いからの生還・その1)03.11.12
ブログ5(悪夢のような船酔いからの生還・その2)03.15.12
ブログ6(悪夢のような船酔いからの生還・その3)03.22.12
ブログ7(悪夢のような船酔いからの生還・その4)03.29.12
ブログ8(一家族6人の小さな島・その1)04.05.12
ブログ9(一家族6人の小さな島・その2)04.12.12
ブログ10(てんぷらを売る・悲哀)04.19.12
今後の公開予定ブログは次の通りです


原則毎週木曜日が公開日。
ブログ11(てんぷらを売る・試行錯誤)
ブログ12(てんぷらを売る・起死回生)
ブログ13(ヤップ島ツァー・マキ公学校)
ブログ14(ヤップ島ツァー・銀河)
ブログ15(てんぷらを売る・まだまだ、半眼)
ブログ16(てんぷらを売る・まだまだ、戸惑い)
ブログ17(てんぷらを売る・まだまだ、言い訳)
ブログ18(てんぷらを売る・まだまだ、課題)
ブログ19(不思議の島モンモン・そう簡単には行けません1)
ブログ20(不思議の島モンモン・そう簡単には行けません2)
ブログ21(不思議の島モンモン・いよいよ上陸)
ブログ22(不思議の島モンモン・後にして)
ブログ23(不思議の島モンモン・その答え?)
「一寸した切掛けで始めたてんぷらの製造販売、
今後どうなって行くか私にも見当が付きませんが、
たとえ頓挫してもありのまま率直に最後の結末まで
書こうと思っています。」とのこと。
「もう一つは離島の多いこの国、
その小さな島に世界の問題の集約された現実を見た思いもしています。
離島を訪ねるチャンスはそう無いのですが、
機会があれば出来るだけ迫りたいと思っています。」
シニア海外ボランティアの活動にご興味のある方は、
ぜひご覧になってみてください

 現在、シニア海外ボランティア募集中
現在、シニア海外ボランティア募集中(4/1~5/14)です!
詳しくはコチラ
 http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html2012年04月23日
地球の裏側・パラグアイ便り
本日、佐賀は、初夏の陽気ですね
今回は、地球の裏側でシニア海外ボランティアとして活動されている
柴田さんからの任国情報です
現在、シニア海外ボランティア募集中(4/1~5/14)です!
詳しくはコチラ http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html






佐賀の皆さん、歓送会をして貰ってから、もう1年7ヶ月が過ぎてしまいました。
早いもので、あと5ヶ月の活動期間です。
私の派遣国、パラグアイ共和国を紹介します。
この国は農牧業が主な産業です。
ある地域では、先日の大雨で農作物が水に浸かり全滅で泣いておられました。
こちらは、季節が日本と正反対です。
今は4月、こちらは秋です。
日本は桜満開の春ですね。
桜に似た花が、こちらでは夏に咲きます。
日本人にとっては変な感じがしますが、
「あー、桜だ」と、バスの窓から眺めます。
日本から移住の人々も、この桜の花に似た、
ラ・パッチョと呼ばれる花を見て、祖国を思い出されていることでしょう。
こちらの習慣で、いつもテレレと呼ばれる、お茶を飲みます。
日本のように、10時、3時の休みにお茶を飲むのではなく、
常にテレレのお茶セットを携行しているのです。
授業中だろうが、
会議中だろうが、
車の運転中だろうが、
テレレの回し飲みするのです。
家では、軒先の木陰で涼みながら
、談話しながら、テレレタイムです。
なんだか、パラグアイの人々の生活は余裕しゃくしゃくのように見えます。
味は苦いです。
漢方薬を飲んでいるようです。
牛肉ばかり食べるから、このテレレが良いのだそうです。
パラグアイの民芸品にニャンドゥティと呼ばれるレース編があります。
ニャンドゥティとは、グァラニー語で蜘蛛の巣と言う意味だそうです。
文字通り蜘蛛の巣のように、放射状にきめ細かく編まれています。
完成するのに、とても時間がかかるそうです。
娘の結婚式のために、一年かけてニャンドゥティのウエディングドレスを作ると言う話を聞いたことがあります。
日本へのお土産は、これに決めました
さて、私の活動の様子をお伝えします。

(配属先の職業訓練短期大学です。
右側のSNPPの看板は強風で吹飛びました!)
配属先は、2年制の職業訓練短期大学の電気科です。

(リレーシーケンス実習盤を学生と一緒に組込んでいます。)
訓練授業のための実習機器等の作成を手伝っています。
現地で手に入る電気部品、資材を購入したり、リサイクル利用しています。
貧しさながらも、学生達は技術を身に付けようと懸命に勉強しています。
私も、負けずと頑張っています。

(展示会の様子です。右奥が私達SNPPのブースで、
エレベーター実習機も展示しています。)
故郷・佐賀の皆さん、もうすぐ帰国報告会でお会いしましょう!

今回は、地球の裏側でシニア海外ボランティアとして活動されている
柴田さんからの任国情報です

現在、シニア海外ボランティア募集中(4/1~5/14)です!
詳しくはコチラ
 http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html





佐賀の皆さん、歓送会をして貰ってから、もう1年7ヶ月が過ぎてしまいました。
早いもので、あと5ヶ月の活動期間です。
私の派遣国、パラグアイ共和国を紹介します。
この国は農牧業が主な産業です。
ある地域では、先日の大雨で農作物が水に浸かり全滅で泣いておられました。
こちらは、季節が日本と正反対です。
今は4月、こちらは秋です。
日本は桜満開の春ですね。
桜に似た花が、こちらでは夏に咲きます。
日本人にとっては変な感じがしますが、
「あー、桜だ」と、バスの窓から眺めます。
日本から移住の人々も、この桜の花に似た、
ラ・パッチョと呼ばれる花を見て、祖国を思い出されていることでしょう。
こちらの習慣で、いつもテレレと呼ばれる、お茶を飲みます。
日本のように、10時、3時の休みにお茶を飲むのではなく、
常にテレレのお茶セットを携行しているのです。
授業中だろうが、
会議中だろうが、
車の運転中だろうが、
テレレの回し飲みするのです。
家では、軒先の木陰で涼みながら
、談話しながら、テレレタイムです。
なんだか、パラグアイの人々の生活は余裕しゃくしゃくのように見えます。
味は苦いです。
漢方薬を飲んでいるようです。
牛肉ばかり食べるから、このテレレが良いのだそうです。
パラグアイの民芸品にニャンドゥティと呼ばれるレース編があります。
ニャンドゥティとは、グァラニー語で蜘蛛の巣と言う意味だそうです。
文字通り蜘蛛の巣のように、放射状にきめ細かく編まれています。
完成するのに、とても時間がかかるそうです。
娘の結婚式のために、一年かけてニャンドゥティのウエディングドレスを作ると言う話を聞いたことがあります。
日本へのお土産は、これに決めました

さて、私の活動の様子をお伝えします。

(配属先の職業訓練短期大学です。
右側のSNPPの看板は強風で吹飛びました!)
配属先は、2年制の職業訓練短期大学の電気科です。

(リレーシーケンス実習盤を学生と一緒に組込んでいます。)
訓練授業のための実習機器等の作成を手伝っています。
現地で手に入る電気部品、資材を購入したり、リサイクル利用しています。
貧しさながらも、学生達は技術を身に付けようと懸命に勉強しています。
私も、負けずと頑張っています。

(展示会の様子です。右奥が私達SNPPのブースで、
エレベーター実習機も展示しています。)
故郷・佐賀の皆さん、もうすぐ帰国報告会でお会いしましょう!
2012年04月13日
『ゴ』と『キラ』ってなんでしょう??
今日は、
ブータンからのお便りです
小学校教諭としてブータンで活動されている立野隊員からです




佐賀のみなさん、クズザンポーラ!!
日本は今、桜の花が満開のお花見シーズンでしょうか?
ブータンでは、ようやく少しずつ暖かくなってきたと思っていたら、
例年より早い雨季に入ったそうです…
雷や雨がひどく、最近はしょっちゅう停電します。
懐中電灯やキャンドルでの生活にもだんだんと慣れてきましたよ。
今回はブータンの衣服 について紹介したいと思います。
について紹介したいと思います。
ブータンでは通学、通勤時は民族衣装の着用が義務付けられています。
男性はゴ、女性はキラと呼ばれる民族衣装を着ています。

(写真①)
どこか懐かしい感じを受けませんか?
そうです、
ブータンの民族衣装は日本の着物にちょっと似ているんですよ!
最初はなかなか着るのが難しかったのですが、
今では普段着にもキラを着ます。
日本の着物や浴衣よりも簡単に着ることができますよ。
また女性の場合、キラ(スカート)、ウォンジュ(ブラウス)、テゴ(ジャケット)の
色の組み合わせを楽しむこともできるんです。
キラに使われている一色をウォンジュやテゴに取り入れ、
統一感をだすのがオシャレなんだとか。
もちろん、制服もゴとキラ。
小さい子は体育の時間の着替えにも一苦労です…

(写真②)
そして、これは正装。
正装時は男性はカムニを、女性はラチュを肩からかけないといけません。

(写真③)
因みに、モンク(お坊さん達)はこんな格好をしています。

(写真④)
自国の衣文化を大切にするブータン人は素敵ですね。
 もっとブータンについて知りたい方は、
もっとブータンについて知りたい方は、
立野隊員のブログをどうぞ~ こちら
こちら
※立野隊員は、国土のほぼ全体が山に覆われ、GNH(国民総幸福量)
という独自の思想を大切にするユニークな国ブータン王国の東部に位置する
カンルンという小さな町の小学校で体育教科の指導を担当しています。
物がない中でどう教え、どう学ばせるのかを常に考えるように。
同僚の先生ともっと協力しながら体育の指導だけに留まらない
発展的活動ができればと考えているんだそうです。
 JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
4/21(土)14:00-16:00 アバンセにて 募集説明会を行います。
問い合わせ:JICAデスク佐賀【(財)佐賀県国際交流協会内】
0952-25-7921(担当:松尾)
JICAボランティアの概要説明のほか、JICAボランティアOBによる体験談や相談を行います。
申し込み不要!途中入退場自由!入場無料!です
ブータンからのお便りです

小学校教諭としてブータンで活動されている立野隊員からです





佐賀のみなさん、クズザンポーラ!!
日本は今、桜の花が満開のお花見シーズンでしょうか?
ブータンでは、ようやく少しずつ暖かくなってきたと思っていたら、
例年より早い雨季に入ったそうです…
雷や雨がひどく、最近はしょっちゅう停電します。
懐中電灯やキャンドルでの生活にもだんだんと慣れてきましたよ。
今回はブータンの衣服
 について紹介したいと思います。
について紹介したいと思います。ブータンでは通学、通勤時は民族衣装の着用が義務付けられています。
男性はゴ、女性はキラと呼ばれる民族衣装を着ています。

(写真①)
どこか懐かしい感じを受けませんか?
そうです、
ブータンの民族衣装は日本の着物にちょっと似ているんですよ!
最初はなかなか着るのが難しかったのですが、
今では普段着にもキラを着ます。
日本の着物や浴衣よりも簡単に着ることができますよ。
また女性の場合、キラ(スカート)、ウォンジュ(ブラウス)、テゴ(ジャケット)の
色の組み合わせを楽しむこともできるんです。
キラに使われている一色をウォンジュやテゴに取り入れ、
統一感をだすのがオシャレなんだとか。
もちろん、制服もゴとキラ。
小さい子は体育の時間の着替えにも一苦労です…

(写真②)
そして、これは正装。
正装時は男性はカムニを、女性はラチュを肩からかけないといけません。

(写真③)
因みに、モンク(お坊さん達)はこんな格好をしています。

(写真④)
自国の衣文化を大切にするブータン人は素敵ですね。
 もっとブータンについて知りたい方は、
もっとブータンについて知りたい方は、立野隊員のブログをどうぞ~
 こちら
こちら※立野隊員は、国土のほぼ全体が山に覆われ、GNH(国民総幸福量)
という独自の思想を大切にするユニークな国ブータン王国の東部に位置する
カンルンという小さな町の小学校で体育教科の指導を担当しています。
物がない中でどう教え、どう学ばせるのかを常に考えるように。
同僚の先生ともっと協力しながら体育の指導だけに留まらない
発展的活動ができればと考えているんだそうです。
 JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、4/21(土)14:00-16:00 アバンセにて 募集説明会を行います。
問い合わせ:JICAデスク佐賀【(財)佐賀県国際交流協会内】
0952-25-7921(担当:松尾)
JICAボランティアの概要説明のほか、JICAボランティアOBによる体験談や相談を行います。
申し込み不要!途中入退場自由!入場無料!です
2012年04月11日
佐賀も、ヨルダンもお花がきれいな季節です♪
みなさま、こんにちは~
ご無沙汰している間に、桜の季節も終わってしまいましたね

(先週、北川副で撮りました )
)
さて、佐賀の桜もきれいなんですが、
ヨルダンからも花の便りが届きました~



(ウンムカイス遺跡)

(アネモネ)

(シクラメン)
これらの写真は、ヨルダンに幼児教育で行かれている
江口隊員から送っていただいた写真です。
ヨルダン北部の『アジュルン』という丘の多い都市で活動されています。
『シクラメン』と『アネモネ』は、江口隊員の家の前の畑に咲いているんだそうです
ヨルダンも今の季節は桜にそっくりなアーモンドや杏の花が咲くんだそうですよ。
ヨルダンの春も日本に負けず劣らず、きれいなんですって
ヨルダンをもっと知りたくなりました!
※江口隊員は、幼稚園の巡回指導をされていて、幼稚園の環境作り、
体育、音楽、美術面などヨルダンの幼児教育に不足していると思われる
活動の技術指導やヨルダンのカリキュラムに沿って
効果的な指導方法を考えられながら活動をされています。
 JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
4/21(土)14:00-16:00 アバンセにて
募集説明会を行います。
問い合わせ:JICAデスク佐賀【(財)佐賀県国際交流協会内】
 0952-25-7921(担当:松尾)
0952-25-7921(担当:松尾)
JICAボランティアの概要説明のほか、JICAボランティアOBによる体験談や相談を行います。
申し込み不要!途中入退場自由!入場無料!です

ご無沙汰している間に、桜の季節も終わってしまいましたね


(先週、北川副で撮りました
 )
)さて、佐賀の桜もきれいなんですが、
ヨルダンからも花の便りが届きました~




(ウンムカイス遺跡)

(アネモネ)

(シクラメン)
これらの写真は、ヨルダンに幼児教育で行かれている
江口隊員から送っていただいた写真です。
ヨルダン北部の『アジュルン』という丘の多い都市で活動されています。
『シクラメン』と『アネモネ』は、江口隊員の家の前の畑に咲いているんだそうです

ヨルダンも今の季節は桜にそっくりなアーモンドや杏の花が咲くんだそうですよ。
ヨルダンの春も日本に負けず劣らず、きれいなんですって

ヨルダンをもっと知りたくなりました!
※江口隊員は、幼稚園の巡回指導をされていて、幼稚園の環境作り、
体育、音楽、美術面などヨルダンの幼児教育に不足していると思われる
活動の技術指導やヨルダンのカリキュラムに沿って
効果的な指導方法を考えられながら活動をされています。
 JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、
JICAボランティア(青年海外協力隊・シニア海外ボランティア)に興味がある方は、4/21(土)14:00-16:00 アバンセにて
募集説明会を行います。
問い合わせ:JICAデスク佐賀【(財)佐賀県国際交流協会内】
 0952-25-7921(担当:松尾)
0952-25-7921(担当:松尾)JICAボランティアの概要説明のほか、JICAボランティアOBによる体験談や相談を行います。
申し込み不要!途中入退場自由!入場無料!です
2012年03月22日
自分にできることを… ベトナムでの活動
こんにちは。
今日は、久しぶりの海外からの活動報告です~
ベトナムのホーチミン市整形外科リハビリテーション病院で
作業療法士として活動されている高尾隊員からです。
4月1日からJICAボランティアの春募集も始まります。
(詳しくは、コチラ)
青年海外協力隊活動の参考にどうぞ
**************(以下、高尾隊員からの報告です)****************
「また高くなった!」
上昇し続ける物価、
建設ラッシュのホーチミンの街。
発展していく国の勢いを肌で感じる毎日。
ベトナムに派遣されて、1年8ヶ月が経ちました。
私は、ホーチミン市整形外科リハビリテーション病院で
作業療法士として活動しています。
今回は、病院以外の場所を回って感じたことを
お伝えします。
孤児院、
養護学校、
地域での訪問リハビリテーション、
貧困地区、
老人ホーム…
協力隊として派遣されて以来、
時間を見つけては、病院以外の場所に
足を伸ばしてきました。
私の配属先とは対照的に、
郊外の施設は支援が届きにくく、
人の出入りが少ない閉鎖的な場所も少なくありません。
その中で、月に1回通っている場所があります。
ホーチミン市からバスで1時間ほど離れた
クチという地方での、リハビリのボランティア活動です。

(クチでのボランティア)
ここでは、以前学校の先生をされていた方の自宅をお借りして、
近くに住む障害児のリハビリを行なっています。
ここにくる子供たちは、金銭的な問題や、
自宅近くに医療・福祉機関がないなど、
リハビリテーションを受ける機会がない子供たちです。
私の他にも、ホーチミン近郊で活動している協力隊の仲間、
その同僚なども一緒に活動しています。
ベトナムは、社会的な背景として、
ベトナム戦争の枯葉剤被害による重複障害児や、
目覚しい発展の中、多発する交通事故によって
障害をかかえた子供たちも少なくありません。

(ホーチミン市はバイクだらけ!)
障害児学校(視覚・聴覚・知的障害学校)
はあるものの、肢体不自由児のための学校が少なく、
多くの重複障害児は、在宅のまま放置されたり、
病院・孤児院に収容され、教育サービスを受けられていない、
という状況下にあります。
私たちは、限られた時間ではありますが、
家族と一緒に、子供の成長を見ていきながら、
情報を交換しあっています。
たとえば都市部では誰もが知っているような
福祉道具も地方に住む人たちは知らないことがたくさんあります。
「子供とどうやって関わったらいいのか?」
「この手はもっと動くようになるのか?」
いろいろな質問を受けます。

(孤児院訪問)
一人でも多くの障害を抱えた子供たちが、
よりよく成長していけるよう、
また、その子供が持っている能力を最大限に引き出せるような
関わりをしていくことができれば、と思っています
今日は、久しぶりの海外からの活動報告です~

ベトナムのホーチミン市整形外科リハビリテーション病院で
作業療法士として活動されている高尾隊員からです。
4月1日からJICAボランティアの春募集も始まります。
(詳しくは、コチラ)
青年海外協力隊活動の参考にどうぞ

**************(以下、高尾隊員からの報告です)****************
「また高くなった!」
上昇し続ける物価、
建設ラッシュのホーチミンの街。
発展していく国の勢いを肌で感じる毎日。
ベトナムに派遣されて、1年8ヶ月が経ちました。
私は、ホーチミン市整形外科リハビリテーション病院で
作業療法士として活動しています。
今回は、病院以外の場所を回って感じたことを
お伝えします。
孤児院、
養護学校、
地域での訪問リハビリテーション、
貧困地区、
老人ホーム…
協力隊として派遣されて以来、
時間を見つけては、病院以外の場所に
足を伸ばしてきました。
私の配属先とは対照的に、
郊外の施設は支援が届きにくく、
人の出入りが少ない閉鎖的な場所も少なくありません。
その中で、月に1回通っている場所があります。
ホーチミン市からバスで1時間ほど離れた
クチという地方での、リハビリのボランティア活動です。

(クチでのボランティア)
ここでは、以前学校の先生をされていた方の自宅をお借りして、
近くに住む障害児のリハビリを行なっています。
ここにくる子供たちは、金銭的な問題や、
自宅近くに医療・福祉機関がないなど、
リハビリテーションを受ける機会がない子供たちです。
私の他にも、ホーチミン近郊で活動している協力隊の仲間、
その同僚なども一緒に活動しています。
ベトナムは、社会的な背景として、
ベトナム戦争の枯葉剤被害による重複障害児や、
目覚しい発展の中、多発する交通事故によって
障害をかかえた子供たちも少なくありません。

(ホーチミン市はバイクだらけ!)
障害児学校(視覚・聴覚・知的障害学校)
はあるものの、肢体不自由児のための学校が少なく、
多くの重複障害児は、在宅のまま放置されたり、
病院・孤児院に収容され、教育サービスを受けられていない、
という状況下にあります。
私たちは、限られた時間ではありますが、
家族と一緒に、子供の成長を見ていきながら、
情報を交換しあっています。
たとえば都市部では誰もが知っているような
福祉道具も地方に住む人たちは知らないことがたくさんあります。
「子供とどうやって関わったらいいのか?」
「この手はもっと動くようになるのか?」
いろいろな質問を受けます。

(孤児院訪問)
一人でも多くの障害を抱えた子供たちが、
よりよく成長していけるよう、
また、その子供が持っている能力を最大限に引き出せるような
関わりをしていくことができれば、と思っています

2012年01月13日
空中都市ラパス!(ボリビア・1月号)
佐賀のみなさん、明けましておめでとうございます
今年の日本の冬は寒いそうですが、
地球の反対側、ここボリビア亜熱帯地域は『焼ける』
を通り越して『焦げる』暑さ が続いています
が続いています
じりじりと照りつくではなく、
ジュージューと焦げ付く天気。
オゾンホールでも開いてるんじゃない
かと思いながら、こんな天気じゃ確かに
誰も仕事なんかしたくなくなるのも仕方ない事・・・
と言ったら負けですね
今年も気合い入れて活動します

さてさて、ついに帰国の年になりました。
残り活動期間70日弱です。
めちゃくちゃ早く感じていますが、
協力隊応募を決意したのが25歳の時、
田舎の組織の役が終わるのを待ちながら勉強を続け、
26になってすぐ応募して訓練を受け27で派遣、
ボリビアで2年間過ごして帰国する時は29歳。
数えてみれば活動自体は2年間とはいえ、
とても長い期間です。
好き勝手やっていた25歳の頃とは考え方も少し変わり、
現在はそろそろ身を固めたいなと思うほどにまでなってしました。
協力隊生活を通して変わったのか、
単に年を重ねた 結果なのか。
結果なのか。
いずれにしろ長かった協力隊生活も後僅かで終わろうとしています。
今回は最近訪ねる機会の多いボリビアの事実上の首都、
ラパスについて少しご紹介しますね。
アルティプラーノと呼ばれる標高4000m程の
広大な台地にぽっかりと空いた谷、
と言ってもそれでも富士山ほどの標高3600mの
土地にある人口85万人(佐賀県の人口と同じくらい。
隣町エル・アルトを含めた首都圏人口は約200万人)程の都市、
それがラパスです。
この不思議な町ラパスはまさに雲上の空中都市。

(ラパスの街並み全景)
標高が高いため照りつく日差しはとても厳しく、
緯度的には熱帯地域に属する位置にあるにもかかわらず
氷点下になる事もしばしば。
気圧が低く沸点が低い為カップラーメンやパスタがおいしく作れず、
圧力鍋でないとご飯もおいしく炊けません。
熱々のコーヒー やお茶
やお茶 も楽しめません。
も楽しめません。
そして恐ろしいのが高山病。
年齢、体力に関わらず発症するこの症状は、
慣れる人はすぐ収まりますが慣れない人にはとても苦しい症状です。
私も初めてラパスに行った時に発症し、
訳も分からないまま気絶してしまいました^^;

(高山病はつらい)

(酸素ボンベ)
こんな過酷な土地ですから、
そこに住む人も競って標高が低い谷底に集まります。
その為高所得者は谷底に、
低所得者は高い山壁に住みつくという普通の土地と逆の現象が起きています。

(山壁をよく見ると…)
さらに最近は増え続けた人口が谷内に収まりきれなくなったため、
アルティプラーノの台地に100万人以上の人々が住んでいます。

(びっしりと建ち並んだ家、家、そして家・・・)
なぜこのような土地に人が集まるのか。

(ラパスの街並み)
歴史をひもとけばちゃんとした理由がありますが、
それを別としてもこの土地の不思議な魅力は人を寄せ付ける魔力があるのではと時々感じてしまいます。

今年の日本の冬は寒いそうですが、
地球の反対側、ここボリビア亜熱帯地域は『焼ける』
を通り越して『焦げる』暑さ
 が続いています
が続いていますじりじりと照りつくではなく、
ジュージューと焦げ付く天気。
オゾンホールでも開いてるんじゃない
かと思いながら、こんな天気じゃ確かに
誰も仕事なんかしたくなくなるのも仕方ない事・・・

と言ったら負けですね

今年も気合い入れて活動します


さてさて、ついに帰国の年になりました。
残り活動期間70日弱です。
めちゃくちゃ早く感じていますが、
協力隊応募を決意したのが25歳の時、
田舎の組織の役が終わるのを待ちながら勉強を続け、
26になってすぐ応募して訓練を受け27で派遣、
ボリビアで2年間過ごして帰国する時は29歳。
数えてみれば活動自体は2年間とはいえ、
とても長い期間です。
好き勝手やっていた25歳の頃とは考え方も少し変わり、
現在はそろそろ身を固めたいなと思うほどにまでなってしました。
協力隊生活を通して変わったのか、
単に年を重ねた
 結果なのか。
結果なのか。いずれにしろ長かった協力隊生活も後僅かで終わろうとしています。
今回は最近訪ねる機会の多いボリビアの事実上の首都、
ラパスについて少しご紹介しますね。
アルティプラーノと呼ばれる標高4000m程の
広大な台地にぽっかりと空いた谷、
と言ってもそれでも富士山ほどの標高3600mの
土地にある人口85万人(佐賀県の人口と同じくらい。
隣町エル・アルトを含めた首都圏人口は約200万人)程の都市、
それがラパスです。
この不思議な町ラパスはまさに雲上の空中都市。

(ラパスの街並み全景)
標高が高いため照りつく日差しはとても厳しく、
緯度的には熱帯地域に属する位置にあるにもかかわらず
氷点下になる事もしばしば。
気圧が低く沸点が低い為カップラーメンやパスタがおいしく作れず、
圧力鍋でないとご飯もおいしく炊けません。
熱々のコーヒー
 やお茶
やお茶 も楽しめません。
も楽しめません。そして恐ろしいのが高山病。
年齢、体力に関わらず発症するこの症状は、
慣れる人はすぐ収まりますが慣れない人にはとても苦しい症状です。
私も初めてラパスに行った時に発症し、
訳も分からないまま気絶してしまいました^^;

(高山病はつらい)

(酸素ボンベ)
こんな過酷な土地ですから、
そこに住む人も競って標高が低い谷底に集まります。
その為高所得者は谷底に、
低所得者は高い山壁に住みつくという普通の土地と逆の現象が起きています。

(山壁をよく見ると…)
さらに最近は増え続けた人口が谷内に収まりきれなくなったため、
アルティプラーノの台地に100万人以上の人々が住んでいます。

(びっしりと建ち並んだ家、家、そして家・・・)
なぜこのような土地に人が集まるのか。

(ラパスの街並み)
歴史をひもとけばちゃんとした理由がありますが、
それを別としてもこの土地の不思議な魅力は人を寄せ付ける魔力があるのではと時々感じてしまいます。
2011年12月08日
暑すぎる12月!ボリビアより
野菜栽培という分野でボリビアで活動している鶴田隊員からの投稿です
ボリビアの12月、
どんな感じなんでしょう?



佐賀の皆さんこんにちは
12月になりましたね。
雪 は降りましたか?
は降りましたか?
ここボリビア亜熱帯アマゾン地域では1年を通して雪が降る事はありません。
それどころかここ最近、日中は40度を超えるほどの強烈に暑い日が続いています。
南米ボリビアは南半球にある国家。
季節は日本と間逆になります。
と言ってもここ亜熱帯アマゾン地域の季節は乾期と雨期しかないのですが、それでもやはり日本では夏である7月がもっとも気温が低い日が多く、逆に雨期に入る前の今の時期が最も暑い日が多くなります。

(これから本格的な雨期。日本ではめったに見ることのない逆さ虹が、ここでは頻繁に発生します)
去年任地サンフアンで行われたクリスマス会でサンタ役を演じたのですが、この煮えたぎるような暑さの中でのサンタ衣装はまさにサウナに炬燵のような組み合わせです。
九州佐賀県で鍛えられた耐暑性程度では乗り越えられるものではありません。
そんなこんなで子供たちには悪いなと思いながらも腕まくりにズボンをたくしあげてサンタを演じたのですが、その光景があまりに印象的だったためか1年たった今でもサンフアンの子供たちにはサンタさんと呼ばれている始末です。

(やさぐれサンタ )
)
そんなうだるような12月ですが、
12月と言えばマンゴーの季節です
早生のマンゴーは既に市場に出回っていますが、特に美味しい品種は12月~2月頃に旬を迎えます。
某有名デパートで売っている宮崎産マンゴー一万円とまったく同じマンゴーがお店で買っても1個20円もしません。
というかその辺になっています。
タダです。
これだけでこの国に移住する価値があるのではないかと心が震えるほどおいしいこのマンゴー

(アップルマンゴー。最高においしい )
)

(これは筋の多いマンゴー。おいしいのですが、一円の価値もありません)
本物の熱帯果樹のおいしさは決して日本では味わう事ができない、幸せの味と言えるのではないでしょうか。
そのかわり、ボリビアでは日本で食べられる最高品質の温帯果樹を食べる事はできませんけどね

ボリビアの12月、
どんな感じなんでしょう?



佐賀の皆さんこんにちは

12月になりましたね。
雪
 は降りましたか?
は降りましたか?ここボリビア亜熱帯アマゾン地域では1年を通して雪が降る事はありません。
それどころかここ最近、日中は40度を超えるほどの強烈に暑い日が続いています。
南米ボリビアは南半球にある国家。
季節は日本と間逆になります。
と言ってもここ亜熱帯アマゾン地域の季節は乾期と雨期しかないのですが、それでもやはり日本では夏である7月がもっとも気温が低い日が多く、逆に雨期に入る前の今の時期が最も暑い日が多くなります。

(これから本格的な雨期。日本ではめったに見ることのない逆さ虹が、ここでは頻繁に発生します)
去年任地サンフアンで行われたクリスマス会でサンタ役を演じたのですが、この煮えたぎるような暑さの中でのサンタ衣装はまさにサウナに炬燵のような組み合わせです。
九州佐賀県で鍛えられた耐暑性程度では乗り越えられるものではありません。
そんなこんなで子供たちには悪いなと思いながらも腕まくりにズボンをたくしあげてサンタを演じたのですが、その光景があまりに印象的だったためか1年たった今でもサンフアンの子供たちにはサンタさんと呼ばれている始末です。

(やさぐれサンタ
 )
)そんなうだるような12月ですが、
12月と言えばマンゴーの季節です

早生のマンゴーは既に市場に出回っていますが、特に美味しい品種は12月~2月頃に旬を迎えます。
某有名デパートで売っている宮崎産マンゴー一万円とまったく同じマンゴーがお店で買っても1個20円もしません。
というかその辺になっています。
タダです。
これだけでこの国に移住する価値があるのではないかと心が震えるほどおいしいこのマンゴー


(アップルマンゴー。最高においしい
 )
)
(これは筋の多いマンゴー。おいしいのですが、一円の価値もありません)
本物の熱帯果樹のおいしさは決して日本では味わう事ができない、幸せの味と言えるのではないでしょうか。
そのかわり、ボリビアでは日本で食べられる最高品質の温帯果樹を食べる事はできませんけどね

2011年12月01日
ブータンは世界一辛い国…らしい(第1回)
みなさま、
今日から12月
師走ですね~
今年も残りわずか。
やらなきゃいけないこと、
やっておきたいこと…
毎年のことながら12月って忙しい月ですね。
ではでは、本題に入りましょう。
世界一辛い国…
それはブータン。
知ってました?
(私、初めて知りました )
)
ブータンといえば
GNPやGDPよりGNH(国民総幸福)を追及している国。
さてさて、どんな国なんでしょうかね~
今年6月より青年海外協力隊の小学校教諭としてブータンに派遣された立野隊員からの情報が入ってまいりましたぁ
(「お気に入り」に立野隊員のブログ《Happy Bhutan'sday》を加えています。
そちらもご覧ください。
協力隊の活動が分かります
そして、ブータンのこと、子供たちのことも
 )
)



佐賀のみなさん、クズザンポーラ(こんにちは)
私は、今年の6月からブータンで小学校教諭として活動しています。
先日のブータン国王・王妃の来日もあり、ブータンという国について関心をもった人も多いのではないでしょうか?
今回はそんなブータンの「食」について紹介したいと思います。
ブータン人の食卓にも欠かせないもの、
それはたっぷりの唐辛子なんです
ブータン料理のほとんどは大量の唐辛子が入っています。
時には、唐辛子に塩だけをつけ、そのまま食べることもあります。
ブータンが、「世界一辛い国」と言われる理由が分かる気がしますよね

(大量の唐辛子の下ごしらえをする少女たち。見るからに辛そう…)
代表的なブータン料理はエマダツィ(唐辛子のチーズ煮込み)です。
エマは唐辛子のこと、ダツィはチーズ煮込みを表します。
その他にも、ジャガイモで作るケワダツィやきのこで作るシャモダツィなどがあります。

(ある日の昼食。ご飯を盛りそこにおかずをのっけるのがブータン流)
ブータン人は毎食のように激辛の唐辛子をおかずに大量のお米をかきこんでいます。
もともと辛い料理が好きな私ですが、それでもブータン料理はとても辛いです…
いまだにお腹を壊してしまうこともしばしばです(笑)
オイリーで塩辛く、激辛のブータン料理、辛いもの好きな人にはぜひ挑戦してほしいですね!

(お弁当を持参する生徒たち。手を使って食べるのがブータンスタイル。
手で食べるのってなかなか難しい…)
また、私の任地であるブータン東部では、アラと言われる地酒でもてなしをするのが一般的です。
とにかく、たくさん飲まされます…
少しでも減るとすぐにまたコップすれすれまでつがれます。
時には、このアラにバターと卵を入れて卵酒のようにする場合もあります。
慣れてくるとマイルドで美味しいですよ。
次回はブータンの「衣」について紹介したいと思います。
今日から12月

師走ですね~

今年も残りわずか。
やらなきゃいけないこと、
やっておきたいこと…
毎年のことながら12月って忙しい月ですね。
ではでは、本題に入りましょう。
世界一辛い国…
それはブータン。
知ってました?
(私、初めて知りました
 )
)ブータンといえば
GNPやGDPよりGNH(国民総幸福)を追及している国。
さてさて、どんな国なんでしょうかね~

今年6月より青年海外協力隊の小学校教諭としてブータンに派遣された立野隊員からの情報が入ってまいりましたぁ

(「お気に入り」に立野隊員のブログ《Happy Bhutan'sday》を加えています。
そちらもご覧ください。
協力隊の活動が分かります

そして、ブータンのこと、子供たちのことも

 )
)


佐賀のみなさん、クズザンポーラ(こんにちは)

私は、今年の6月からブータンで小学校教諭として活動しています。
先日のブータン国王・王妃の来日もあり、ブータンという国について関心をもった人も多いのではないでしょうか?
今回はそんなブータンの「食」について紹介したいと思います。
ブータン人の食卓にも欠かせないもの、
それはたっぷりの唐辛子なんです

ブータン料理のほとんどは大量の唐辛子が入っています。
時には、唐辛子に塩だけをつけ、そのまま食べることもあります。
ブータンが、「世界一辛い国」と言われる理由が分かる気がしますよね


(大量の唐辛子の下ごしらえをする少女たち。見るからに辛そう…)
代表的なブータン料理はエマダツィ(唐辛子のチーズ煮込み)です。
エマは唐辛子のこと、ダツィはチーズ煮込みを表します。
その他にも、ジャガイモで作るケワダツィやきのこで作るシャモダツィなどがあります。

(ある日の昼食。ご飯を盛りそこにおかずをのっけるのがブータン流)
ブータン人は毎食のように激辛の唐辛子をおかずに大量のお米をかきこんでいます。
もともと辛い料理が好きな私ですが、それでもブータン料理はとても辛いです…

いまだにお腹を壊してしまうこともしばしばです(笑)
オイリーで塩辛く、激辛のブータン料理、辛いもの好きな人にはぜひ挑戦してほしいですね!

(お弁当を持参する生徒たち。手を使って食べるのがブータンスタイル。
手で食べるのってなかなか難しい…)
また、私の任地であるブータン東部では、アラと言われる地酒でもてなしをするのが一般的です。
とにかく、たくさん飲まされます…

少しでも減るとすぐにまたコップすれすれまでつがれます。
時には、このアラにバターと卵を入れて卵酒のようにする場合もあります。
慣れてくるとマイルドで美味しいですよ。
次回はブータンの「衣」について紹介したいと思います。
2011年11月24日
野菜栽培で国際協力!@エジプト
突然ですが、
青年海外協力隊員に興味があるあなた、
国際協力に興味があるあなた
そんあなたのためにちょっとだけ
協力隊について説明。
(秋募集が終わったばっかりなんですけどねー )
)
青年海外協力隊は、大きく9つの分野から国際協力を行っています。
9つの分野とは、農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、スポーツ、計画・行政。
細かく分けて行くと120以上の職種があるんですよー
自分の持っている知識や経験を生かしていただくわけですが、特に資格が必要ない職種もあります。
詳細はこちら http://www.jica.go.jp/volunteer/(JICAボランティアHP)
http://www.jica.go.jp/volunteer/(JICAボランティアHP)
で、今回はその中の一つ、農林水産部門の中の野菜栽培という職種で参加している杉町隊員からの活動紹介です。




私はエジプトのベニスエイフ県ガーファル村に野菜栽培隊員として派遣されています。
任期も2011年12月いっぱいで終わりなのでそろそろ活動も終盤に差し掛かっています。
村の人たちはとても親切でガーファル村に続く道すがら、すれ違う人全員から挨拶されます。
「おはよう、調子はどうだい?」とか
「紅茶飲んでいけよ」とか
「結婚はまだか、娘を日本に連れて帰ってもいいぞ」などなど。
1日がそういったやりとりから入るのでとても気持ちが穏やかになりながら村に活動しに行くことができます。

(エジプトは葡萄が有名)

(外で遅い朝食を)
いまガーファル村では冬野菜の収穫と来年に向けた作物の種の播種を行なっています。
冬野菜はレタス、ほうれん草、カリフラワー、人参、ルッコラ、ネギ、カブが収穫されています。種の播種は小麦を主に行なっています。
小麦は来年の4月から5月にかけて収穫されます。

(インゲンマメ畑)
エジプトは世界的にも小麦の生産が盛んです。
エジプトの主食はパンなので、だいたい、市場や街中でパンを買い求めるために朝から行列ができるほどです。
さて、私の活動も終盤に差し掛かってきました。
今は、畑に出て農民と一緒に冬野菜の収穫をお手伝いしたり、コンポスト(堆肥)の生産をカウンターパートと一緒に行なっています。コンポストの質を良くしたり、生産量を増やすための工夫を配属先と話し合いながら進めています。
あと少しの間ですが、村の農業がより良くなるために農民と刺激し合いながら活動を続けていきたいと思います。

(わんぱくな子供たち)
青年海外協力隊員に興味があるあなた、
国際協力に興味があるあなた
そんあなたのためにちょっとだけ
協力隊について説明。
(秋募集が終わったばっかりなんですけどねー
 )
)青年海外協力隊は、大きく9つの分野から国際協力を行っています。
9つの分野とは、農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、スポーツ、計画・行政。
細かく分けて行くと120以上の職種があるんですよー

自分の持っている知識や経験を生かしていただくわけですが、特に資格が必要ない職種もあります。
詳細はこちら
 http://www.jica.go.jp/volunteer/(JICAボランティアHP)
http://www.jica.go.jp/volunteer/(JICAボランティアHP)で、今回はその中の一つ、農林水産部門の中の野菜栽培という職種で参加している杉町隊員からの活動紹介です。




私はエジプトのベニスエイフ県ガーファル村に野菜栽培隊員として派遣されています。
任期も2011年12月いっぱいで終わりなのでそろそろ活動も終盤に差し掛かっています。
村の人たちはとても親切でガーファル村に続く道すがら、すれ違う人全員から挨拶されます。
「おはよう、調子はどうだい?」とか
「紅茶飲んでいけよ」とか
「結婚はまだか、娘を日本に連れて帰ってもいいぞ」などなど。
1日がそういったやりとりから入るのでとても気持ちが穏やかになりながら村に活動しに行くことができます。

(エジプトは葡萄が有名)

(外で遅い朝食を)
いまガーファル村では冬野菜の収穫と来年に向けた作物の種の播種を行なっています。
冬野菜はレタス、ほうれん草、カリフラワー、人参、ルッコラ、ネギ、カブが収穫されています。種の播種は小麦を主に行なっています。
小麦は来年の4月から5月にかけて収穫されます。

(インゲンマメ畑)
エジプトは世界的にも小麦の生産が盛んです。
エジプトの主食はパンなので、だいたい、市場や街中でパンを買い求めるために朝から行列ができるほどです。
さて、私の活動も終盤に差し掛かってきました。
今は、畑に出て農民と一緒に冬野菜の収穫をお手伝いしたり、コンポスト(堆肥)の生産をカウンターパートと一緒に行なっています。コンポストの質を良くしたり、生産量を増やすための工夫を配属先と話し合いながら進めています。
あと少しの間ですが、村の農業がより良くなるために農民と刺激し合いながら活動を続けていきたいと思います。

(わんぱくな子供たち)
2011年10月28日
日本にニカラグアを紹介しよう!
ニカラグアで青年海外協力隊の小学校教諭として活動されている山下隊員からの投稿です
佐賀県の皆さん、こんにちは
ニカラグア共和国からです
私はニカラグアのレオン県レオン市にあるJohn.F.Kennedy小学校で算数教育の向上を主な目的とした協力活動を行っています。
先日、2年A組と幼稚園の年長組の子どもたちと図工の時間を使って合作作品制作をしました。
私は、特技の「書」で参加しました。
2年A組でのテーマは
「日本の人々にNicaraguaを紹介しよう!!」
人数が多いため、2グループに分かれて制作しました。

(完成!)
幼稚園の年長組でのテーマは
「日本の人々に自己紹介をしよう!!」

(完成!)
家庭の事情により児童1人1人が、
絵の具やクレヨンを買うことができないため、
各担任が「私達でクレヨンを集めてくるから!!」と言って下さり、児童全員が楽しく制作することができました。
また、児童の中には「私のクレヨンも使っていいよ!!」と友達に貸す姿も見受けられました。
(↓制作風景)



現在、この作品は佐賀県鳥栖駅の構内に展示されています。 ↓↓↓



ニカラグアと日本の絆を感じる温かい作品ですね。
山下さん、ありがとうございました

佐賀県の皆さん、こんにちは

ニカラグア共和国からです

私はニカラグアのレオン県レオン市にあるJohn.F.Kennedy小学校で算数教育の向上を主な目的とした協力活動を行っています。
先日、2年A組と幼稚園の年長組の子どもたちと図工の時間を使って合作作品制作をしました。
私は、特技の「書」で参加しました。
2年A組でのテーマは
「日本の人々にNicaraguaを紹介しよう!!」
人数が多いため、2グループに分かれて制作しました。

(完成!)
幼稚園の年長組でのテーマは
「日本の人々に自己紹介をしよう!!」

(完成!)
家庭の事情により児童1人1人が、
絵の具やクレヨンを買うことができないため、
各担任が「私達でクレヨンを集めてくるから!!」と言って下さり、児童全員が楽しく制作することができました。
また、児童の中には「私のクレヨンも使っていいよ!!」と友達に貸す姿も見受けられました。
(↓制作風景)



現在、この作品は佐賀県鳥栖駅の構内に展示されています。 ↓↓↓




ニカラグアと日本の絆を感じる温かい作品ですね。
山下さん、ありがとうございました

2011年10月24日
野菜の妖精…チョリータさん!@ボリビア(10月号)
今月もボリビアで活動している鶴田隊員からの投稿です
今回は、かわいらしいお話
私もおさげ髪したくなりました~



佐賀のみなさんこんにちは。
今日は常夏のアマゾン地域にて、
寒冷なアンデスの民族衣装で生活を行う女性について紹介しますね。
民族衣装と言うと日本の着物のように特別な時にしか着ないような印象を受けますよね。
たしかにある程度はその通りで、
伝統文化を守るために民族衣装を着続けると主張している人もいます。
ですがここボリビアではそれほど深い理由なく、
多くの人が普段着として着ているようです。
この地で暮らす人々にとって
民族衣装は当たり前の格好であり、
もちろん野良仕事も民族衣装のまま行います。
何百年という長い歴史を乾燥した寒冷な高地で暮らしてきたアンデスの人々は、その気候にあった服装を着こなしてきました。
モコモコのスカートにツインのおさげ髪、
リャマの毛で作った肩掛けにカラフルな風呂敷、
そして特徴的な山高帽をかぶったケチュア、
アイマラ等のアンデス民族の女性たちは
チョリータさん
と呼ばれています。

(お祭りチョリータさん)
チョリータさんが住んでいるのは高地だけではありません。
特にここ数十年の間の移民プロジェクトにより、
沢山のチョリータさんが過酷な環境の高地より温暖で豊かな低地に移住し、生活しています。
私の活動対象もそんなチョリータさん達が中心です。
彼女たちの多くもチョリータファッションを愛用していますが、
高地の衣装はここアマゾン地域では暑過ぎ。

(暑さ対策のチョリータさん!)
そこで伝統的な見た目を残しながらも、
ここアマゾン地域のチョリータさんは
山高帽を麦わら帽子に、
モコモコのスカートをミニスカに
履き替え暑い地域に対応したファッションを着こなしています。

(おさげが似合ってます )
)
私の生徒達である野菜の妖精たち。みんな素敵でしょ?


今回は、かわいらしいお話

私もおさげ髪したくなりました~




佐賀のみなさんこんにちは。
今日は常夏のアマゾン地域にて、
寒冷なアンデスの民族衣装で生活を行う女性について紹介しますね。
民族衣装と言うと日本の着物のように特別な時にしか着ないような印象を受けますよね。
たしかにある程度はその通りで、
伝統文化を守るために民族衣装を着続けると主張している人もいます。
ですがここボリビアではそれほど深い理由なく、
多くの人が普段着として着ているようです。
この地で暮らす人々にとって
民族衣装は当たり前の格好であり、
もちろん野良仕事も民族衣装のまま行います。
何百年という長い歴史を乾燥した寒冷な高地で暮らしてきたアンデスの人々は、その気候にあった服装を着こなしてきました。
モコモコのスカートにツインのおさげ髪、
リャマの毛で作った肩掛けにカラフルな風呂敷、
そして特徴的な山高帽をかぶったケチュア、
アイマラ等のアンデス民族の女性たちは
チョリータさん
と呼ばれています。

(お祭りチョリータさん)
チョリータさんが住んでいるのは高地だけではありません。
特にここ数十年の間の移民プロジェクトにより、
沢山のチョリータさんが過酷な環境の高地より温暖で豊かな低地に移住し、生活しています。
私の活動対象もそんなチョリータさん達が中心です。
彼女たちの多くもチョリータファッションを愛用していますが、
高地の衣装はここアマゾン地域では暑過ぎ。

(暑さ対策のチョリータさん!)
そこで伝統的な見た目を残しながらも、
ここアマゾン地域のチョリータさんは
山高帽を麦わら帽子に、
モコモコのスカートをミニスカに
履き替え暑い地域に対応したファッションを着こなしています。

(おさげが似合ってます
 )
)私の生徒達である野菜の妖精たち。みんな素敵でしょ?

2011年09月15日
諸問題。。。@ボリビア(9月号)
佐賀の皆さんこんにちは
南米ボリビアの農業隊員、鶴田です。
今月はボリビアが抱えている問題をいくつか紹介しますね。
まずは野焼きのお話。
南米アマゾンでは年間どこかの土地(適当で申し訳ありません)に匹敵するくらいの広さの森林が消えているという話をよく聞きますよね。
ここボリビアでも盛大に森が消えまくっています。
そしてそのほとんどは開拓目的の人為的火災によって焼失しています。

(人の手によって燃やされた国立公園の様子)
森林の消失も重大な問題なのですが、
同様に問題なのがその火災によって放出される膨大な量の煙。
地平線が見えるほどまっ平らなここサンフアンで、
雲ひとつない晴天にも関わらず、
この時期は500m先ですら霞んで見えます。
そう、野焼きの煙が原因です。
想像できますか?
遠い森林が燃えているため立ち上る煙が見えないにも関わらず、広大な地域のどこに行っても煙が充満しているのです。
太陽は一日中夕焼けの様な色をしていて、
ひどい日には飛行機が飛べなくなるほど熱帯アマゾン地域は煙でいっぱいになります。
煤けたような臭いが漂い、のどの粘膜が弱い人はせきが止まらなくなり、
洗濯物は洗い直さなければ臭いが染み付いてしまいます。
よくない事だとわかっているのに止められない。
こういった問題はボリビアに限った事では無いのですが…
最後に環境問題について少しだけ。
先日、長距離バスに乗った時の出来事です。
出発の時間になって、バスの運転手より乗客に対し、
次の様な乗車中の注意がありました。
「乗客の皆さん、ご乗車ありがとうございます。
バス内においての飲食は自由となっていますが、
ゴミをバス内に残さないようご協力お願いします。
先日、バスの点検を行っていると荷物棚から大量のゴミが出てきました。
最近の乗客は本当にマナーが悪い!
ゴミはちゃんとバスの外に捨ててください。」
といいながら運転手は窓を開け、
ゴミを投げ捨てるジェスチャーを行いました。
窓からのポイ捨てはこの国では当たり前の光景。
常識であって、マナー違反ではないと言う事なのでしょうか。
今回はネガティブな話ばかりになってしまいましたね
次回は明るい話題を提供できればと思います。
それではまた


南米ボリビアの農業隊員、鶴田です。
今月はボリビアが抱えている問題をいくつか紹介しますね。
まずは野焼きのお話。
南米アマゾンでは年間どこかの土地(適当で申し訳ありません)に匹敵するくらいの広さの森林が消えているという話をよく聞きますよね。
ここボリビアでも盛大に森が消えまくっています。
そしてそのほとんどは開拓目的の人為的火災によって焼失しています。

(人の手によって燃やされた国立公園の様子)
森林の消失も重大な問題なのですが、
同様に問題なのがその火災によって放出される膨大な量の煙。
地平線が見えるほどまっ平らなここサンフアンで、
雲ひとつない晴天にも関わらず、
この時期は500m先ですら霞んで見えます。
そう、野焼きの煙が原因です。
想像できますか?
遠い森林が燃えているため立ち上る煙が見えないにも関わらず、広大な地域のどこに行っても煙が充満しているのです。
太陽は一日中夕焼けの様な色をしていて、
ひどい日には飛行機が飛べなくなるほど熱帯アマゾン地域は煙でいっぱいになります。
煤けたような臭いが漂い、のどの粘膜が弱い人はせきが止まらなくなり、
洗濯物は洗い直さなければ臭いが染み付いてしまいます。
よくない事だとわかっているのに止められない。
こういった問題はボリビアに限った事では無いのですが…
最後に環境問題について少しだけ。
先日、長距離バスに乗った時の出来事です。
出発の時間になって、バスの運転手より乗客に対し、
次の様な乗車中の注意がありました。
「乗客の皆さん、ご乗車ありがとうございます。
バス内においての飲食は自由となっていますが、
ゴミをバス内に残さないようご協力お願いします。
先日、バスの点検を行っていると荷物棚から大量のゴミが出てきました。
最近の乗客は本当にマナーが悪い!
ゴミはちゃんとバスの外に捨ててください。」
といいながら運転手は窓を開け、
ゴミを投げ捨てるジェスチャーを行いました。
窓からのポイ捨てはこの国では当たり前の光景。
常識であって、マナー違反ではないと言う事なのでしょうか。
今回はネガティブな話ばかりになってしまいましたね

次回は明るい話題を提供できればと思います。
それではまた


2011年09月05日
胎盤(たいばん)食べますか?@中国
今日は、お隣の国「中国」からおもしろ情報をゲットしました
情報をくれたのは、中国で幼児教育の活動をされている鶴田隊員です
中国三大かまどの1つ・重慶は、今年も40℃以上の灼熱地獄


エアコン設備のない学校が多い為、
本来9月1日の始業式は行政命令(高温休暇)で1週間延期されました。
先日、同僚が双子を出産
中国の一人っ子政策は有名ですが、
幼稚園の子どもにも兄弟がいる子は沢山います。
両親が漢族で一人っ子同士の夫婦は子どもを2人持つ事を許され、
少数民族は制限なし。
「自由に子どもを産める日本人は幸せだね!」と、言われます。
中国の妊婦さんは産後1ヶ月家事をしません。
”座月子(ズォユエズ)”直訳すると座って1ヶ月を過ごす、
という昔の習慣が残っています。
産後の体をゆっくり休めるためで、1ヶ月はお風呂に入らず、歯磨きもしないそうです。
「衛生的にどうなの!?」思いますが、
体を冷やさない為と外からの感染を防ぐ為だとか。
当時の水は消毒されてない等の影響かもしれません。
座月子期間中の子育ては専門のベビーシッターに任せます。
出産直後「彼女の胎盤を食べに行こう!」と誘われました。
胎盤は非常に栄養価が高く、子どもを授かる縁起物とされています。
中国には、
”足が4本ある物は机と椅子以外何でも食べる、
空を飛ぶ物は飛行機以外何でも食べる”
という言葉がありますが、
まさか人体の一部だった物まで食べるとは…
中国の食文化にまた驚かされた出来事でした。
(本人の胎盤かどうか不確かな上、HIVや肝炎等に感染する危険性もあるので、私は食べていません。)
さて、10月半ばに任期終了となる私の協力隊生活。

(配属先の幼稚園で、子供たちと)
この2年の間には、
尖閣問題や対中ODAへの厳しい風当たり、
そして東日本大震災…
正直モチベーションが下がる出来事もありましたが、
日本にいたら考えなかったであろう事、
日本を出たからこそ気付けた日本の幼児教育の素晴らしさ等、
日本人として、そして教育者として貴重な経験をさせて頂きました。
無事健康に帰国の日を迎えられる事に感謝しています。

(赴任当初からかかわってきた子供たちとの卒園記念写真)

 まだまだ鶴田さんのお話しをご覧になりたい方は
まだまだ鶴田さんのお話しをご覧になりたい方は

↓こちらのブログをご覧ください
笑口常開~いつも笑顔で~ http://blog.livedoor.jp/xiaoli_0102/
鶴田さん自身がされているブログです。
活動の様子がわかる(子供たちがすごくかわいいんです )だけでなく、日本と中国の教育の違い、考えの違いが幼稚園の先生としての目線で書かれているので、またおもしろいですよ。
)だけでなく、日本と中国の教育の違い、考えの違いが幼稚園の先生としての目線で書かれているので、またおもしろいですよ。

情報をくれたのは、中国で幼児教育の活動をされている鶴田隊員です

中国三大かまどの1つ・重慶は、今年も40℃以上の灼熱地獄



エアコン設備のない学校が多い為、
本来9月1日の始業式は行政命令(高温休暇)で1週間延期されました。
先日、同僚が双子を出産

中国の一人っ子政策は有名ですが、
幼稚園の子どもにも兄弟がいる子は沢山います。
両親が漢族で一人っ子同士の夫婦は子どもを2人持つ事を許され、
少数民族は制限なし。
「自由に子どもを産める日本人は幸せだね!」と、言われます。
中国の妊婦さんは産後1ヶ月家事をしません。
”座月子(ズォユエズ)”直訳すると座って1ヶ月を過ごす、
という昔の習慣が残っています。
産後の体をゆっくり休めるためで、1ヶ月はお風呂に入らず、歯磨きもしないそうです。
「衛生的にどうなの!?」思いますが、
体を冷やさない為と外からの感染を防ぐ為だとか。
当時の水は消毒されてない等の影響かもしれません。
座月子期間中の子育ては専門のベビーシッターに任せます。
出産直後「彼女の胎盤を食べに行こう!」と誘われました。
胎盤は非常に栄養価が高く、子どもを授かる縁起物とされています。
中国には、
”足が4本ある物は机と椅子以外何でも食べる、
空を飛ぶ物は飛行機以外何でも食べる”
という言葉がありますが、
まさか人体の一部だった物まで食べるとは…
中国の食文化にまた驚かされた出来事でした。
(本人の胎盤かどうか不確かな上、HIVや肝炎等に感染する危険性もあるので、私は食べていません。)
さて、10月半ばに任期終了となる私の協力隊生活。

(配属先の幼稚園で、子供たちと)
この2年の間には、
尖閣問題や対中ODAへの厳しい風当たり、
そして東日本大震災…
正直モチベーションが下がる出来事もありましたが、
日本にいたら考えなかったであろう事、
日本を出たからこそ気付けた日本の幼児教育の素晴らしさ等、
日本人として、そして教育者として貴重な経験をさせて頂きました。
無事健康に帰国の日を迎えられる事に感謝しています。

(赴任当初からかかわってきた子供たちとの卒園記念写真)

 まだまだ鶴田さんのお話しをご覧になりたい方は
まだまだ鶴田さんのお話しをご覧になりたい方は

↓こちらのブログをご覧ください

笑口常開~いつも笑顔で~ http://blog.livedoor.jp/xiaoli_0102/
鶴田さん自身がされているブログです。
活動の様子がわかる(子供たちがすごくかわいいんです
 )だけでなく、日本と中国の教育の違い、考えの違いが幼稚園の先生としての目線で書かれているので、またおもしろいですよ。
)だけでなく、日本と中国の教育の違い、考えの違いが幼稚園の先生としての目線で書かれているので、またおもしろいですよ。
2011年09月01日
母校のプロジェクト参加(日本とのつながり)
いよいよ今日から9月ですね。
まだまだ暑い日 が続いていますが、彼岸花も咲きだし、少しずつ秋が近づいているようです
が続いていますが、彼岸花も咲きだし、少しずつ秋が近づいているようです
今回は、チリで環境教育として活動
(活動については、7月28日投稿の記事をご参照ください )している
)している
古川隊員からの投稿です。

(第2弾!)
 母校のプロジェクト参加
母校のプロジェクト参加
私の母校である武雄北中学校では、
夢プロジェクトという企画を実施していて、
その1つが「夢ハンカチ」。
東北関東大震災の被災地に元気を送るため、
様々な人の夢を規定のハンカチに書いて(描いて)もらい、
それを10月までに1万枚集めて贈るというもの。
それに私も任地の子供達と参加をしている。

(どんな夢を描いているのでしょう???)
中学校の教頭先生が特殊なハンカチをわざわざチリまで送ってくれて、私が学校で授業をする際に時間をもらって実施中。
チリでも1年半前に大地震があったのもあり、みんなとても協力的だ。
わが国日本にとってとても大変な時期に、日本にいない日本人として何ができるのか考え悩むことがあるけど、母校の後輩達のプロジェクトに参加することで少しは遠くからも何かができるという、自己満足の世界でもあるが、感謝している。

(素敵な夢が描けました )
)
まだまだ暑い日
 が続いていますが、彼岸花も咲きだし、少しずつ秋が近づいているようです
が続いていますが、彼岸花も咲きだし、少しずつ秋が近づいているようです
今回は、チリで環境教育として活動
(活動については、7月28日投稿の記事をご参照ください
 )している
)している古川隊員からの投稿です。


(第2弾!)
 母校のプロジェクト参加
母校のプロジェクト参加私の母校である武雄北中学校では、
夢プロジェクトという企画を実施していて、
その1つが「夢ハンカチ」。
東北関東大震災の被災地に元気を送るため、
様々な人の夢を規定のハンカチに書いて(描いて)もらい、
それを10月までに1万枚集めて贈るというもの。
それに私も任地の子供達と参加をしている。

(どんな夢を描いているのでしょう???)
中学校の教頭先生が特殊なハンカチをわざわざチリまで送ってくれて、私が学校で授業をする際に時間をもらって実施中。
チリでも1年半前に大地震があったのもあり、みんなとても協力的だ。
わが国日本にとってとても大変な時期に、日本にいない日本人として何ができるのか考え悩むことがあるけど、母校の後輩達のプロジェクトに参加することで少しは遠くからも何かができるという、自己満足の世界でもあるが、感謝している。

(素敵な夢が描けました
 )
)
2011年08月22日
ボリビア観光の参考に。。。
ボリビアの鶴田隊員からの投稿です。
みなさんこんにちは
南米ボリビアの鶴田です。
今回はボリビアの観光についてご紹介しますね。
雄大なアンデス山脈と広大なアマゾン川、古代インカ文明とスペインの侵略。
豊かな自然と深い歴史を持つ国ボリビアですが、観光方面でもまだまだ発展途上の国です。
自然や遺跡の数々、文化に安価な物価などなど魅力満載の国なのですが、アピールする力が足りません。
みなさんはボリビアと聞いて何を思い浮かべますか?
正しく南米にあると言える方自体少ないのではないでしょうか?
昨年はウユニ塩原(塩湖)やエケコ人形が騒がれたので少し名前が売れたのですが、ブームが過ぎ去った今記憶していらっしゃる方はあまり多くないでしょう。

(乾期のウユニ)
観光地としてはあまり有名ではないボリビア、
しかしそれは単に宣伝や整備など観光開発が整っていないためで、ボリビアという国が持つ観光ポテンシャルは世界有数の底力を持っている事は間違いありません。
例として世界遺産であるアルゼンチンのロス・グラシアレス(氷河)(写真上)と、同じく世界遺産であるボリビアのエル・フエルテ(遺跡)の遊歩道(写真下)を見比べてみましょう。


どちらがアルゼンチンで、どちらがボリビアかは一目瞭然です。
まぁ、ボリビアの歩道これはこれで温かみがあるようにも見えますがよく見てください。
このやる気のない板の並べ方!
頼りないてすり!
その辺の公園の歩道ならいざ知らず、観光客を集めお金を稼ぐ絶好の観光資源、世界遺産でこのレベルなのです。
なんてもったいない!
景観を守るために木材を使うのは素晴らしい心構えですが(そのつもりで使ったのではないでしょうが)、だからと言ってこの適当さはあきれます^^;
こんな感じで観光方面でも実にもったいない国ボリビアですが、もったいないながらも素晴らしい観光地でいっぱいです。
JICAの指示で休暇の話はできないようになっているため詳しくお伝えできないのが残念ですが、私も配属先が認めてくださっている年間20日間の休暇を利用し何か所かの観光地を訪ねました。
そのうちいくつかの写真を紹介させていただきますね^^

(サマイパタ エル・フエルテ遺跡)

(月の谷)
化石燃料、レアメタル、観光・・・海こそありませんがボリビアは世界有数の資源大国です。
だからと言う本音を出すのはいけませんが、外交戦略的にも日本が仲良くするべき国ですよね。
あ、いやいや、もちろん世界中の国と仲良くしなきゃいけませんけどね!
あまり本音を書くとJICAに怒られるので今回はこの辺で^^
それではまた来月!

(おまけ )
)
みなさんこんにちは

南米ボリビアの鶴田です。
今回はボリビアの観光についてご紹介しますね。
雄大なアンデス山脈と広大なアマゾン川、古代インカ文明とスペインの侵略。
豊かな自然と深い歴史を持つ国ボリビアですが、観光方面でもまだまだ発展途上の国です。
自然や遺跡の数々、文化に安価な物価などなど魅力満載の国なのですが、アピールする力が足りません。
みなさんはボリビアと聞いて何を思い浮かべますか?
正しく南米にあると言える方自体少ないのではないでしょうか?
昨年はウユニ塩原(塩湖)やエケコ人形が騒がれたので少し名前が売れたのですが、ブームが過ぎ去った今記憶していらっしゃる方はあまり多くないでしょう。

(乾期のウユニ)
観光地としてはあまり有名ではないボリビア、
しかしそれは単に宣伝や整備など観光開発が整っていないためで、ボリビアという国が持つ観光ポテンシャルは世界有数の底力を持っている事は間違いありません。
例として世界遺産であるアルゼンチンのロス・グラシアレス(氷河)(写真上)と、同じく世界遺産であるボリビアのエル・フエルテ(遺跡)の遊歩道(写真下)を見比べてみましょう。


どちらがアルゼンチンで、どちらがボリビアかは一目瞭然です。
まぁ、ボリビアの歩道これはこれで温かみがあるようにも見えますがよく見てください。
このやる気のない板の並べ方!
頼りないてすり!
その辺の公園の歩道ならいざ知らず、観光客を集めお金を稼ぐ絶好の観光資源、世界遺産でこのレベルなのです。
なんてもったいない!
景観を守るために木材を使うのは素晴らしい心構えですが(そのつもりで使ったのではないでしょうが)、だからと言ってこの適当さはあきれます^^;
こんな感じで観光方面でも実にもったいない国ボリビアですが、もったいないながらも素晴らしい観光地でいっぱいです。
JICAの指示で休暇の話はできないようになっているため詳しくお伝えできないのが残念ですが、私も配属先が認めてくださっている年間20日間の休暇を利用し何か所かの観光地を訪ねました。
そのうちいくつかの写真を紹介させていただきますね^^

(サマイパタ エル・フエルテ遺跡)

(月の谷)
化石燃料、レアメタル、観光・・・海こそありませんがボリビアは世界有数の資源大国です。
だからと言う本音を出すのはいけませんが、外交戦略的にも日本が仲良くするべき国ですよね。
あ、いやいや、もちろん世界中の国と仲良くしなきゃいけませんけどね!
あまり本音を書くとJICAに怒られるので今回はこの辺で^^
それではまた来月!

(おまけ
 )
)
2011年08月09日
作業療法士というシゴト@ベトナム
みなさま、こんにちは
最近、セミの声の大きさが一段と増していると思うのは、私だけでしょうか。
(最後の力を振り絞っているんでしょうね)
しかし、暑い
今回は、作業療法士として活動されている高尾さんの活動紹介です。
作業療法士という職業がないベトナムでどのような活動をされているのか???
ぜひご覧ください
こんにちは。
高尾麻衣子と申します。
私は、福岡県にある病院で4年働いた後、現職参加制度を利用し、職場を休職させていただき、この青年海外協力隊に参加しています。
現在は、ホーチミン市にある障害児整形外科リハビリセンターで作業療法士として活動しています。
ベトナムにはまだ作業療法士という職業がなく、発達障害領域の子供を対象に、正しい作業療法知識に基づく治療・訓練の 質の向上を図る目的で、派遣されました。
配属先のセンターは、たくさんの緑に囲まれた、とても魅力的な場所です。
スタッフ数約70名(同僚の理学療法士10名含む)、ベッド数約120床、その他、子供のデイケアや外来リハビリに来る子供たちで、センター内はいつも活気に満ち溢れています。また、たくさんの外国人ボランティアの出入りがあり、地域に開かれたセンターです。
私の1日の活動は、主に外来の子供のリハビリと、デイケアの子供のお世話・日常生活動作訓練(食事・着替えなど)です。
デイケアには、16歳未満の約40名の子供たちが通ってきています。
配属された当初一番驚いたのは、この子供たちがバイクで送り迎えされていることでした。
バイクの上で姿勢を保てない子は、両親の間に挟まれていたり(3人乗りで)、抱っこ紐のようなもので、しっかりと抱えられ、やってきていました。日本では考えられません。
子供たちは、先天性の病気や、交通事故により障害を抱えています。
戦争時の枯葉剤の影響を受けている子もいると言われていますが、証明することが難しく、保障を受けることができるのは、ほんの一握りだと聞きました。
また、交通事故が多いのもベトナムの特徴だと思います。、世界1位と言われているバイクの数、交通マナーも悪く、いくら注意していても、ヒヤリとするような出来事によく遭遇します。

(バイクの嵐…)
日々活動する中で感じたことは、技術を伝えるつもりできていたけど、逆に教わることも多くあったということ。
乏しい語学力、人間関係、1人ではなにもできないことを実感させられ、周りと協力することの大切さを改めて感じました。
また、子供たちの笑顔がかわいすぎるということ。
わたしの1番の元気の源です!!

さて、私はベトナムに来て1年が経ちました。
環境にもなれ、活動も落ち着いてきました。
今後の目標は、少し視野を広くしセンターの外に眼を向けてみることです。
障害を持つ子供たちが、地域社会(自宅、学校、社会)に適応する際の手助け、また、金銭面や、重度の障害で病院にこれない子供たちと関わることができれば、と考えています。
最後に、戦後成長し続けるベトナム、その経済の中心ホーチミン市の活気を、肌で感じることができるのも貴重な経験です。
物価がどんどん上がっていく…、そのスピードに少々驚きつつも、めまぐるしく変わっていくこの魅力溢れるベトナム生活を楽しんでいきたいと思っています。

(朝食の定番「フォー」)
残りの活動期間、1年、頑張っていきたいと思います!

最近、セミの声の大きさが一段と増していると思うのは、私だけでしょうか。
(最後の力を振り絞っているんでしょうね)
しかし、暑い

今回は、作業療法士として活動されている高尾さんの活動紹介です。
作業療法士という職業がないベトナムでどのような活動をされているのか???
ぜひご覧ください

こんにちは。
高尾麻衣子と申します。
私は、福岡県にある病院で4年働いた後、現職参加制度を利用し、職場を休職させていただき、この青年海外協力隊に参加しています。
現在は、ホーチミン市にある障害児整形外科リハビリセンターで作業療法士として活動しています。
ベトナムにはまだ作業療法士という職業がなく、発達障害領域の子供を対象に、正しい作業療法知識に基づく治療・訓練の 質の向上を図る目的で、派遣されました。
配属先のセンターは、たくさんの緑に囲まれた、とても魅力的な場所です。
スタッフ数約70名(同僚の理学療法士10名含む)、ベッド数約120床、その他、子供のデイケアや外来リハビリに来る子供たちで、センター内はいつも活気に満ち溢れています。また、たくさんの外国人ボランティアの出入りがあり、地域に開かれたセンターです。
私の1日の活動は、主に外来の子供のリハビリと、デイケアの子供のお世話・日常生活動作訓練(食事・着替えなど)です。
デイケアには、16歳未満の約40名の子供たちが通ってきています。
配属された当初一番驚いたのは、この子供たちがバイクで送り迎えされていることでした。
バイクの上で姿勢を保てない子は、両親の間に挟まれていたり(3人乗りで)、抱っこ紐のようなもので、しっかりと抱えられ、やってきていました。日本では考えられません。
子供たちは、先天性の病気や、交通事故により障害を抱えています。
戦争時の枯葉剤の影響を受けている子もいると言われていますが、証明することが難しく、保障を受けることができるのは、ほんの一握りだと聞きました。
また、交通事故が多いのもベトナムの特徴だと思います。、世界1位と言われているバイクの数、交通マナーも悪く、いくら注意していても、ヒヤリとするような出来事によく遭遇します。

(バイクの嵐…)
日々活動する中で感じたことは、技術を伝えるつもりできていたけど、逆に教わることも多くあったということ。
乏しい語学力、人間関係、1人ではなにもできないことを実感させられ、周りと協力することの大切さを改めて感じました。
また、子供たちの笑顔がかわいすぎるということ。
わたしの1番の元気の源です!!

さて、私はベトナムに来て1年が経ちました。
環境にもなれ、活動も落ち着いてきました。
今後の目標は、少し視野を広くしセンターの外に眼を向けてみることです。
障害を持つ子供たちが、地域社会(自宅、学校、社会)に適応する際の手助け、また、金銭面や、重度の障害で病院にこれない子供たちと関わることができれば、と考えています。
最後に、戦後成長し続けるベトナム、その経済の中心ホーチミン市の活気を、肌で感じることができるのも貴重な経験です。
物価がどんどん上がっていく…、そのスピードに少々驚きつつも、めまぐるしく変わっていくこの魅力溢れるベトナム生活を楽しんでいきたいと思っています。

(朝食の定番「フォー」)
残りの活動期間、1年、頑張っていきたいと思います!
2011年07月28日
任地の活動@チリ(おまけつき)
厳しい暑さ が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、初登場の古川隊員 からの投稿です
からの投稿です
古川さんは、昨年12月からチリに環境教育隊員として派遣されています。
環境教育???
ということで、どんな活動をされているのか、活動の一部を紹介していただきました
学校が主な活動場所となっています。
ごみのリサイクルや分解年数を学ぶ授業をしています。
↓↓牛乳パック(その他、ワインやジュースのパック)をフリスビーにして遊んだ授業。

下の写真は、様々なごみが何年かかって分解するのかという授業をした後に、生徒にその絵と分解年数を書いてもらいました。

(ぼくたち、上手にかけたでしょ )
)
この後、みんなが描いた絵は、廊下に掲示しました。


 おまけ―日本と似ているところ―
おまけ―日本と似ているところ―


 チリの女性は、大人も子供もトイレに2人以上で行くことが一般的らしい。
チリの女性は、大人も子供もトイレに2人以上で行くことが一般的らしい。
そうそう。日本に似ていますね
特に学生時代とか。
今後の古川さんからの投稿をお楽しみに~
 が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。今回は、初登場の古川隊員
 からの投稿です
からの投稿です
古川さんは、昨年12月からチリに環境教育隊員として派遣されています。
環境教育???
ということで、どんな活動をされているのか、活動の一部を紹介していただきました

学校が主な活動場所となっています。
ごみのリサイクルや分解年数を学ぶ授業をしています。
↓↓牛乳パック(その他、ワインやジュースのパック)をフリスビーにして遊んだ授業。

下の写真は、様々なごみが何年かかって分解するのかという授業をした後に、生徒にその絵と分解年数を書いてもらいました。

(ぼくたち、上手にかけたでしょ
 )
)この後、みんなが描いた絵は、廊下に掲示しました。


 おまけ―日本と似ているところ―
おまけ―日本と似ているところ―


 チリの女性は、大人も子供もトイレに2人以上で行くことが一般的らしい。
チリの女性は、大人も子供もトイレに2人以上で行くことが一般的らしい。そうそう。日本に似ていますね

特に学生時代とか。
今後の古川さんからの投稿をお楽しみに~

2011年07月11日
今、ボリビアは冬です!(7月号)
みなさま、
ついに梅雨明けしましたね~
夏本番 です
です
日本とは真逆の冬 のボリビアから
のボリビアから
(ちょっとうらやましい )
)
鶴田隊員の活動紹介です
みなさんこんにちは。伊万里の梨農家です。
地元伊万里で梨の出荷が始まる季節になりました。
セミは鳴き始めたでしょうか?
いよいよ日本は夏本番ですね。
北半球にある日本の反対、南半球にあるここボリビアには『寒い南風』の吹き荒れる冬が訪れています。冬とは言っても南風のない日の気温は25度前後ですけどね。そして寒い日でも氷点下になる事はありません。もちろん雪も降りません。
先日職場の中庭にナマケモノが1匹迷い込んでいました。

(↑本物のナマケモノ!!)
カタツムリといい勝負ができそうなくらい怠けている動物なのですが、いったいいつの間にどのようにして忍びこんだのでしょうか。
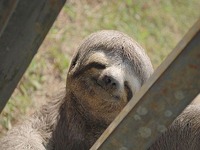
(←微笑んでいるみたい )
)
ゆったりとした動きを見ていると時間がとても長く感じられます。
今回も前回に引き続き活動の様子を紹介しますね。
まだまだ農業経験の浅い人間が付け焼刃の語学力で活動を行えるほどですので、指導対象である派遣先の地域の人々の技術力はあまり高くありません。それこそ土づくりや栽培管理以前に、水の撒き方、種の蒔き方、スコップの使い方からと指導する事は沢山あります。
何度言っても移植を終えたばかりの苗にバケツの水をひっくり返して水撒きをしたり、逆に水不足で枯らした野菜を指して、「病気になった。消毒してくれ」と言ったり・・・どうしてこのくらいの事もわかってくれないのかと不満に思う事は山ほどあります。

そんなこんなで偉そうに農業技術を教えている私ですが、
教える事よりも学ぶことのほうが多く、
私自身も活動先の人々から怒られる事しばしば(汗)
初めて見た熱帯の果樹がなんであるかわからなかったり、マチェテと呼ばれる巨大ナイフの使い方が下手だと言われたり。
教え教われな毎日です。
女の子の口説き方や下ネタもそこはラテンの国、
日常会話として飛び交います。
奥手な日本人である私にとってはそういう面でも学ぶ事は沢山あります。
いや、実践する事はないですけどね(笑)
熱帯地域の農業は温帯地域である日本の農業と違う事も多く、私が持っている知識だけでは手に負えない事が多々あります。また農業の地域差に限らずとも派遣先の人々のほうが私より優れている事は沢山あります。
マチェテの使い方もそうですが、栽培方法や管理方法等でも私が学ぶべき事は沢山です。
日本の農家でマンゴー等熱帯果樹の剪定や
接ぎ木を行った事がある人はどのくらいいるでしょうか。
巨大なナイフを振り回して草刈りを行った事がある人はどのくらいいるでしょうか。
これらの経験は今後の人生において実際に役に立つ事がなかったとしても、大きな財産となる事間違いなしだと思っています。
人との出会いは自分の人生の豊かさに繋がると、最近強く感じるようになりました。
そして経験はそのまま、人生の豊かさになると感じています。
この協力隊活動中に知り合った多くの人々との出会いはどれも私にとって素晴らしいものでした。
もちろん良い出会いばかりであったわけではありませんけど…
それもまた経験として^^;
残り9カ月となった協力隊活動。
私がこの経験や出会いから様々な事を学び人生を豊かにしているように、私と関わってくれる人々の人生の豊かさに私が影響を与えることができますように。

ついに梅雨明けしましたね~

夏本番
 です
です
日本とは真逆の冬
 のボリビアから
のボリビアから(ちょっとうらやましい
 )
)鶴田隊員の活動紹介です

みなさんこんにちは。伊万里の梨農家です。
地元伊万里で梨の出荷が始まる季節になりました。
セミは鳴き始めたでしょうか?
いよいよ日本は夏本番ですね。
北半球にある日本の反対、南半球にあるここボリビアには『寒い南風』の吹き荒れる冬が訪れています。冬とは言っても南風のない日の気温は25度前後ですけどね。そして寒い日でも氷点下になる事はありません。もちろん雪も降りません。
先日職場の中庭にナマケモノが1匹迷い込んでいました。

(↑本物のナマケモノ!!)
カタツムリといい勝負ができそうなくらい怠けている動物なのですが、いったいいつの間にどのようにして忍びこんだのでしょうか。
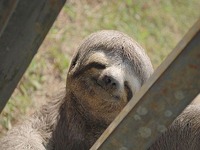
(←微笑んでいるみたい
 )
)ゆったりとした動きを見ていると時間がとても長く感じられます。
今回も前回に引き続き活動の様子を紹介しますね。
まだまだ農業経験の浅い人間が付け焼刃の語学力で活動を行えるほどですので、指導対象である派遣先の地域の人々の技術力はあまり高くありません。それこそ土づくりや栽培管理以前に、水の撒き方、種の蒔き方、スコップの使い方からと指導する事は沢山あります。
何度言っても移植を終えたばかりの苗にバケツの水をひっくり返して水撒きをしたり、逆に水不足で枯らした野菜を指して、「病気になった。消毒してくれ」と言ったり・・・どうしてこのくらいの事もわかってくれないのかと不満に思う事は山ほどあります。

そんなこんなで偉そうに農業技術を教えている私ですが、
教える事よりも学ぶことのほうが多く、
私自身も活動先の人々から怒られる事しばしば(汗)
初めて見た熱帯の果樹がなんであるかわからなかったり、マチェテと呼ばれる巨大ナイフの使い方が下手だと言われたり。
教え教われな毎日です。
女の子の口説き方や下ネタもそこはラテンの国、
日常会話として飛び交います。
奥手な日本人である私にとってはそういう面でも学ぶ事は沢山あります。
いや、実践する事はないですけどね(笑)
熱帯地域の農業は温帯地域である日本の農業と違う事も多く、私が持っている知識だけでは手に負えない事が多々あります。また農業の地域差に限らずとも派遣先の人々のほうが私より優れている事は沢山あります。
マチェテの使い方もそうですが、栽培方法や管理方法等でも私が学ぶべき事は沢山です。
日本の農家でマンゴー等熱帯果樹の剪定や
接ぎ木を行った事がある人はどのくらいいるでしょうか。
巨大なナイフを振り回して草刈りを行った事がある人はどのくらいいるでしょうか。
これらの経験は今後の人生において実際に役に立つ事がなかったとしても、大きな財産となる事間違いなしだと思っています。
人との出会いは自分の人生の豊かさに繋がると、最近強く感じるようになりました。
そして経験はそのまま、人生の豊かさになると感じています。
この協力隊活動中に知り合った多くの人々との出会いはどれも私にとって素晴らしいものでした。
もちろん良い出会いばかりであったわけではありませんけど…
それもまた経験として^^;
残り9カ月となった協力隊活動。
私がこの経験や出会いから様々な事を学び人生を豊かにしているように、私と関わってくれる人々の人生の豊かさに私が影響を与えることができますように。

2011年07月04日
ヒマラヤがみえる街
みなさん、こんにちは
7月突入です。2011年も半分が過ぎました!
う~ん、しかし、まだ、梅雨明けしそうにありませんね~
今回は、ネパールのポカラ市。
村落開発普及員として今年1月からネパールで頑張っている武藤さんからの投稿です。
ポカラはネパールで2番目の都市で一番の観光地です。
↓晴れた日は街のいたる所からヒマラヤが見えます。
ネパールは
日本米やしょうゆなんかも
簡単に手に入ります
ネパール人は
能天気な日本人って感じです
部族によっては顔もそっくりです

↑ホーリーというお祭り
大人も子供も
カラーボールをぶつけあいます

先日ブッタの生まれた場所である
ルンビニに行ってきました
世界各国がルンビニに仏教寺をつくって
世界平和を祈っているようなところで
まさにシャンティでした
日本の仏舎利塔もありました
武藤さん、ありがとうございました
仏舎利塔、なんと佐賀にもあります!
牛津の「肥前仏舎利塔」。(当たり前かもしれませんが、ルンビニの仏舎利塔に似ています)
ネパールを身近に感じました
では、次回は、どこの国からの投稿がくるでしょうか?
お楽しみに!

7月突入です。2011年も半分が過ぎました!
う~ん、しかし、まだ、梅雨明けしそうにありませんね~

今回は、ネパールのポカラ市。
村落開発普及員として今年1月からネパールで頑張っている武藤さんからの投稿です。
ポカラはネパールで2番目の都市で一番の観光地です。
↓晴れた日は街のいたる所からヒマラヤが見えます。

ネパールは
日本米やしょうゆなんかも
簡単に手に入ります
ネパール人は
能天気な日本人って感じです
部族によっては顔もそっくりです

↑ホーリーというお祭り
大人も子供も
カラーボールをぶつけあいます

先日ブッタの生まれた場所である
ルンビニに行ってきました
世界各国がルンビニに仏教寺をつくって
世界平和を祈っているようなところで
まさにシャンティでした
日本の仏舎利塔もありました
武藤さん、ありがとうございました

仏舎利塔、なんと佐賀にもあります!
牛津の「肥前仏舎利塔」。(当たり前かもしれませんが、ルンビニの仏舎利塔に似ています)
ネパールを身近に感じました

では、次回は、どこの国からの投稿がくるでしょうか?
お楽しみに!