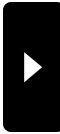2011年06月20日
グアテマラのケーキはいかが?

みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
ちょっとでも異国の気分を味わってもらい、憂鬱な梅雨を忘れてください

今回は、中南米のグアテマラです。
青少年活動として児童施設で活動している鈴田有加さんからの「ここがびっくり!グアテマラ情報」です


↑グアテマラのケーキ
 (外国らしいケーキですね~)
(外国らしいケーキですね~)青・黄・赤…味はともかく(笑)すご~くきれいです!!(鈴田さん談)
色もすごいけど、大きさもすごい
 …直径50センチあるらしい
…直径50センチあるらしい

グアテマラでは、1日2回のおやつタイム(10時と4時)には、甘ーい飲み物とお菓子やパン。おやつって量ではなくご飯並みの量(笑)だそう
 でも、昔は体が大きい方が富の象徴で、今もその名残が残っているとのこと。
でも、昔は体が大きい方が富の象徴で、今もその名残が残っているとのこと。開発途上国でも、栄養不良の問題と合わせ、栄養過多による生活習慣病(糖尿病や高血圧、肥満など)が問題になっています。
食生活を変えるといっても、「太っているのが富の象徴」と言った考えなど、その国の風習・文化・社会環境や生活環境などなど…が絡んでくると、そう簡単にはいかないものですよね。
次回のグアテマラ情報、お楽しみに~

追伸:鈴田さん、野犬
 (グアテマラは野犬がすごく多いんですって)に気をつけてくださいね
(グアテマラは野犬がすごく多いんですって)に気をつけてくださいね2011年06月01日
ボリビアだより
いよいよ今日から6月ですね

梅雨がないボリビアから前回に続き、便りが届きました

今回も面白い写真が届いてますよ~

それではどうぞ~
みなさんこんにちは。ボリビアで活動を行っている協力隊兼伊万里市の梨農家です。今回は活動の紹介をさせていただきます。
自宅のあるサンフアン日系人移住地より北へ。


道端に転がっている大蛇やワニを眺めながらぼこぼこのアスファルトと
日本の無償援助で建設された橋を超え、そこから先は雨期になると沼、乾期になると砂漠になる未舗装の道を進みます。日本ではあまり見ることのできない見渡す限り水平な大地を、ああ俺協力隊やってるなぁと感じながら進む事40km。ザ・協力隊活動場所といった感じの集落「アヤクチョ」に到着です。

この集落が現在の主な活動先です。
この集落はアンデス山脈で暮らしていたケチュアという民族の方々が豊かな自然を求めて移り住んで来てできた比較的新しい集落で、政府の移住プロジェクトで移住してきた家族にはなんと各家族50ha(1へクタール=100m×100m、我が家の農地の10倍以上!)もの土地がプレゼント(?)されています。それでも皆さん土地が狭いとご不満の様子。土地の利用率、農業の効率が良くないため50haの土地を遊ばせちゃっているのが現状です。それらの改善と、持続可能な農業の伝達が私の活動の大きな課題となっています。
持続可能な農業を確立する事は農家にとってはもちろんですが、これからの世界全体のためにも必要な事でしょう。
わかりやすい例としてボリビアでも問題になっている焼き畑農業があります。森を焼き払い農地を作り、農地がやせ衰えたらまた新しく森を焼き払い農地を作る事によって続いているこの農法、時期によっては煙害で飛行機が飛ばない日があるほどそれはそれは燃えまくりなのですが、このままではアマゾンのジャングルは砂漠になっちゃいます。これは極端な例であり私の活動は直接的には焼き畑を防ぐ事には繋がりませんが、持続可能な農業を行う事により将来性のある農業経営ができると伝える事ができればと思っています。

自宅のあるサンフアン移住地は地元伊万里市大川町より都会(?)なため、赴任当初は想像していた協力隊像とのギャップに少し戸惑いを覚えていました。収入こそ日本の人々より少ないですが(多い方ももちろんいます)その分生活費が安価なためそれぞれの生活は日本より豊かにすら見えます。そういう事もあってか、初めて巡回指導を行った日は失礼な表現ですが感動すら覚えました。途上国も豊かなところはとても豊かですが、少し町を離れると沢山の貧しい人々が生活を行っています。
鶏の横で昼寝をする猫、その枕になっている犬、自分をその兄弟だと思っている猪、日本ではまず見ることのできないのどかな風景。

ここではそれが当り前です。
そしてその土地で貧しいながらも明るく暮らす人々。
彼らに協力し、ほんのわずかではあっても彼らの人生が豊かになる力となり、彼らとともに自分自身も成長する事ができる。
うーん、なんと素晴らしい機会でしょうか。
決して無駄にしてはいけませんね^^

2011年05月12日
ボリビアでも佐賀弁が通じる?!
そしてそして、ご無沙汰しておりました

今回は、ボリビアで野菜栽培で活動されている鶴田 善久隊員からの報告です。
みなさんこんにちは。

南米ボリビアにおいて協力隊活動を行っている伊万里の梨農家です。今回は任地であるサンタクルス県サンフアン市の紹介をさせていただきますね。
サンフアン市は日系移住地として開拓され発展してきた人口1万人程の町で、現在も250件800名ほどの日系人の方がこの町で生活を行っています。多くの方が九州、特に長崎出身の方で、佐賀県出身の方も何名かおられます。そのためサンフアンでは当たり前のように佐賀弁が通じちゃいます。
それどころか、この町で生まれ育った私と同年代の日系3世たちの会話の中にも佐賀弁が出てきます。彼らサンフアンの日系人は当たり前のように日本語とスペイン語をまぜこぜにして話すバイリンガルなのですが、その会話の中に時々出てくる佐賀弁を聞くといつもほっとしちゃいます。
スペイン語で『私』にあたる一人称は『Yo(ヨ)』なのですが、サンフアン人の若者たちは日本語で話す時も『私』のかわりにこの『Yo』をよく使います。
例えば「私の名前は~です」は「Yoの名前は~です」といった感じですね。この『Yo』がサンフアンに来たばかりの頃は『余』に聞こえてしまって、いつも心の中でどこの上様ですか(笑)とつっこんでいました。
「余も遊ぶ~~(゚∀゚)」とか言っているちっちゃな将軍たちを見るととてもほのぼのしてしまいますよ。

サンフアンの日系人たちは多大な努力をもって裕福な生活を築き上げることに成功しました。
移住当時はジャングルだった土地を切り開き、周りのボリビア人よりもずっと貧しい生活を行いながらも着実に前進を続け、今では米・養鶏を中心とした農産物の生産でボリビア経済に貢献するほどまでに成長しています。
経済的差が大きくなると外の国から移住してきた人々は以前よりその地に住んでいた人々から妬みに似た感情を覚えられる事も少なくありませんが、多大な努力の上での成功である事を周囲の人々も理解しているため彼らサンフアンの日系人はむしろ羨望や憧憬に近い友好的な評価を受けています。
私の主な活動先はサンフアン日系人移住区より40km程離れた、高地より移り住んだ方々が暮らす日系人移住区より新しい集落です。
そのため直接的には活動の要請内容はサンフアンの日系社会を対象としていません。
事実配属されるその時までサンフアンという町がここまで「日本」であることを知りませんでしたし、日々の生活でスペイン語より佐賀弁を話す機会が多くなるとは思っていませんでした。ですが偶然か運命か巡り合う事になったこのサンフアン日系社会、私の人生において大きな財産となるこの出会いを大切にし、いつかここサンフアンが自分の第二の故郷であると胸を張れるように馴染む事ができればと思っています。

2011年03月29日
ニカラグアから応援メッセージ②

東北関東大震災での被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
東北関東大震災は、ニカラグア国内にも大きな衝撃が走りました。また、ニカラグアの太平洋沖にも津波がくるという予報を受けて国内でも軍隊を動員して津波に備えていました。幸い、ニカラグアには大きな津波はきませんでした。
私の周辺のニカラグア人は「自国のことよりも日本のことを本当に心配」していました。
私が活動しているジョン・F・ケネディー小学校は、私でボランティアが3代目ということもあり、副校長でもあり私のカウンターパートでもあるラモン先生が「日本の皆さんに何かしたい!!」と言ってくれました。
そこで、一緒に応援メッセージを作ろう!と計画をしました。

カメラの都合で児童達が国旗を描いている様子と私が書を書いている様子を写真に収めることはできませんでしたが・・・。
主に6年生と作り上げました。他の学年の教室をまわった際に、児童皆が「私が書きたい!」と言ってくれて放課後も「日本のために書きたい!!」と、たくさんの児童が言ってくれました。

それから、教員みんな・保護者の方々・警察官・ホームステイ先の家族、たくさんの人々が日本にメッセージを送りたいと言ってくれました。
メッセージの内容は「日本とニカラグアは兄弟。1日も早い復興を神に祈っています。」「神は、きっと日本を救ってくれる。」「共に歩んでいこう。」「心は1つ。」等です。

被災された皆様、1日も早い復興を心から願っています。

ニカラグア
山下 優子
2011年03月28日
ニカラグアから東北への応援メッセージ
再び、とても温かい、そして励まされるニュースがありました。
現在ニカラグアに派遣されている山下優子さんから、配属先の小学校で、東北大震災の応援メッセージが届きました。
東北での津波、大地震はニカラグアでも大きなニュースになっていて、ニカラグアの人々は本当に日本のことを心配しているそうです。
「何かしたい!!!」
その思いから、山下さんが配属されている小学校で日本への応援メッセージを作ってくれたそうです。
その際に、児童たちも教員たちも、日本へ応援メッセージを書きたい!と言ってくれたそうです。
日本の反対側にあるニカラグアからも、日本は応援されていることを感じ、とても心があたたかくなりました。
写真では見えづらいですが、日本語やスペイン語で、東北、日本の復興を願うメッセージがぎっしり込められています。
今現在は、佐賀県庁のワールドプラザに掲示していますが、今後、佐賀県協力隊を育てる会のメンバーが東北へボランティアへ向かう際に、みんなの応援の気持ちとともに持って行ってもらう予定です。
ニカラグアからの思いが、東北の被災者の心へ届く事を願って・・・☆

2011年03月25日
中国から東北大震災への募金活動
現在中国へ青年海外協力隊として派遣中の鶴田さゆりさん(平成21年度2次隊、職種:幼児教育)から
のお便りがありました。
以下、お読みください

このたび、東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々とご遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。
また、被災された皆様、ご家族の方々に心からお見舞い申し上げます。
被災されました地域におかれましては、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
私が地震発生を知ったのは、金曜日の夕方。
職員室で授業準備をしていた時でした。
ケータイにJICA中国事務所から電話が入り、CPが使っているPCを譲ってもらってネットのニュースを見たけど。
あの時は、今回の地震がここまでひどいとは正直思っていませんでした。
週末、私のケータイはずっと鳴りっ放し。
心配した同僚や保護者・子ども達からのものでした。
「私の実家は無事だよ。家族も、友達も。ありがとう。」
何度も何度も言ってると、”自分さえよければいいのか!”と思えてきました。
国の一大事に、国外でぬくぬくとしている自分が嫌になってきて。
こんな時に何もできなくて…誰がボランティアなんだ!って。
週明け幼稚園に行くと、先生達が「実家は無事だった?」と次々に聞いてきてくれて。
「なにか出来ることがあったら、なんでも言ってね!」って言ってくれるけど、そんなの私にもわかりません。
気にかけてくれるのは嬉しいけど、何だか複雑な気分でした。
自分の実家や地元・身の回りは大丈夫だけど、日本は大丈夫じゃないから。
子ども達も、自宅のTVで見たのでしょう。
「先生、日本で地震があったって知ってる?」という子
「ママに”笑理老師に優しくしてあげなさい”って言われたよ」という子
「日本は危ないから、このままずっと中国にいなよ」という子
「お家が直るまで、ウチに泊まっていいよ!」という子
この子、何度言って聞かせても私が毎日日本から飛行機通勤してると思ってます。
そして、昨日3月17日。
去年の配属クラスで工作の授業をする事になってたのですが、授業の前にあなたに話があると言われました。
「今、私達は日本の大地震にとても注目してる。
この子達が中班(年中組)の頃、四川大地震が起きた時、あなたの前任者が日本の幼稚園に呼びかけてバザーをして中国を助けてくれた。
今度は、私達が日本を助ける番よ!」
授業の前に、担任の王老師から言われた言葉です。
いつもは騒がしい子ども達も、この時は真剣な眼差しで王老師の話を聞いていました。
地震が起きてからというもの、こっちの人達が私や日本の事を気に掛けてくれるのは非常に嬉しく思いました。
しかし、顔を合わせる度に地震の話をされるのが、何だか億劫で…。
幼稚園の食堂でご飯を食べている時に地震の話をされる時には、食糧難や水不足の被災地の事を思い浮かべてしまって・・・。
協力隊という1つのボランティアの身分でありながら、節電の協力もできなければ、献血も出来ない。
優しい言葉で気遣ってくれる子ども達、沢山いました。
「明日、先生にお金あげるね~!」と言って帰っていきます。
「その言葉だけで十分、ありがとう。」そう言って送り出す私。
その日、私がこのクラスで授業をする事に合わせ、王老師が私に内緒で子ども達(各家庭)に募金を募ってくれていたのでした。
それまで、どんな悲惨な映像や写真・ニュースを見てもなかなか実感がわかず、
”国外にいて実質的な苦労を共にしてない私には泣く資格は無いし、泣いたってどうしようも無い!”と思ってきた私ですが、子ども達の目の前で大泣き・・・。
今日、このクラスで集まった募金は約2000元。
(日本円に換算すると約3万円ですが、中国の一般家庭約1ヶ月分の収入に相当する金額)
写真でははっきり見えないかもしれませんが、黒板には”日本加油!~頑張れ日本!~”と、書かれています。

園長室に行き、今日の出来事とそれに対する感謝の気持ちを伝えに行きました。
「当然の事をしただけだから、気を遣わないで。それにしても、いい考えだわ。
このクラスだけじゃなくて、南坪実験幼稚園全体で募金活動をしましょう!
1クラスで2000元集まったんだから、全体でやったらもっと大きな力になるわよ!」
と言って下さり、お迎えの時間募金してくれたクラスに行き、お迎えに来られた保護者1人1人に募金協力へのお礼を言った時も「当然の事よ。」ほとんどの保護者がそう言って下さり、何も言わない代わりに私の肩を優しく撫でて下さった方も。
担任の王老師は、「今回の地震の報道を見て、日本人を本当に尊敬してる。
シャオリーが授業をする時、どんなに時間がかかろうと”並ぶ””待つ””譲り合う””ありがとうと言う習慣”…etc
正直、何でこんな事に時間を割くの?授業を進めた方がいいんじゃない?そう思いながらあなたの授業を見てた事もあったの。
でも、あなたが日本の幼稚園でやってた様に、授業を効率良くやる事より、こういう内面の部分を根気良く子ども達に教えているかがわかった気がする。
小さい頃からこれをやり続けてるからこそ、日本人は今回みたいな困難に遭っても秩序を保って、お互いを思いやった行動ができるんだと思う。
あなたがいつも教えている事、子ども達が大きくなっても忘れないで欲しい。
そして、私達も伝えていかなきゃね。」そう言ってくれました。
こんな時だからこそ、日本にいようが国外にいようが、自分の日本人としての本質が問われるのかもしれません。

今、私に出来る事は日本に一時帰国する事ではなく、協力隊としての活動を全うする事です。
(私のブログ⇒http://blog.livedoor.jp/xiaoli_0102/)
日本にいなくとも、離れていても、日本を思ってくれている人たちが大勢いる・・・。
今回を機に、理論ではなく、世界が助け合う事・人種を超えて互いを思いやる、人のあたたかさを心から実感しました。
今回の募金活動は配属先が実施してくれたもので、鶴田さん自身から投げ掛けたものではないそうです。
そして、今日鶴田さんから連絡があったのですが、
たった1日にして、中国人一家3ヶ月分の生活費が集まったそうです。
鶴田さんは、「大量のお札を数える時、普通なら笑いが止まらなくなるのでしょうが、私の場合は涙が止まりませんでした」と話されていました。
「国際協力」をしに、協力隊として派遣され、しかし、逆に日本が助けられている。
世界は一つなんだと、本当に相互依存・お互いが協力し合う事の大切さを、より一層感じている今日この頃です。
2011年03月15日
ベトナムだより
先週起こった地震・津波で、深刻な被害が出ていて、ニュースを見るたびに心が痛む思いをしています。
地震が起きたとき、私は海外にいたのですが、現地の人も「日本は大丈夫か?」「家族や友人は大丈夫か?」「日本人はとても優しく親切だから、被害がひどくならないように祈るよ」・・・などといった言葉を会う人会う人から聞きました。
九州は今回、影響はなかったけれども、それでも、同じ日本、同じ地球に住む者として、みんなが被災者の方々を応援している、励ましていて、世界は一つなのだと改めて実感しています。
私も佐賀にいてもできる身近なことから始めてみようと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、今回はベトナムに派遣されている高尾麻衣子さんからのお便りです

高尾さんはH22年6月に派遣されました。約9ヶ月たつ今、どのような生活をされているのでしょうか?
ではごゆっくりお読みください^^
みなさんこんにちは。
ベトナムに作業療法士として活動している高尾麻衣子と申します。
私は、ベトナムの食事を紹介したいと思います。
食事は人間が生活していく上で非常に大切なものです。
食べることが大好きな私は、協力隊に参加するにあたり、食事面の心配は非常に大きいものでした。
しかし派遣される前、ベトナムの情報誌で、ベトナムの食事は、フランスと中国の影響を受けていることや、豊かな食材に溢れていることを知り、不安は解消され、楽しみになっていました。
実際に来て感じたことは、ベトナムの食事は、おいしすぎる!!ということです。味付けは日本の味と似ているものも多くあります。
ついつい食べすぎでしまいます。日本では食べることのできない、野菜・果物も豊富にあります。
日本にいるとき、私は毎日お菓子を大量に食べてましたが、今は新鮮な果物、シントー、チェーなど、現地の作りたてのおやつを安く食べることができており、お菓子を食べる量が減りました!私にとって食事は、楽しみの場、コミュニケーションの場、ストレス解消の場です。
ベトナムの食事の特徴は、外食が多いこと、大皿につがれたおかずをみんなで分け合って食べること、お米をたくさん食べるところだと思います。
代表的なベトナム料理は、麺料理のフォーや、生春巻きなどです。
私は、朝昼の食事を同僚とともにします。夜は、隣に呼ばれることも多いです。どこで食事をしても、みんなは「たくさん食べなさい」と言い、料理をよそってくれます。人の優しさを感じる瞬間です。
時間があるときは、わたしも負けじと日本食を作り紹介しています。味の問題は別として、みんなとても喜んでくれます。
これからも食事を通して、ベトナムを知り、また日本を伝えていけたらいいなと思います。…もちろん活動も頑張っていますよ!!

2011年03月01日
モロッコから学ぶこと
今日はアフリカ、モロッコからお便りが届いていますのでご紹介します


はじめまして。
北アフリカに位置するモロッコに村落開発普及員として配属されている蒲地里奈です。
これからたまにこうしてブログにお邪魔することになると思いますが、
よろしくお願いします。
何を書こうか迷いましたが、最初に私がここで学んだ“ものの見方”について書きたいと思います。
モロッコ人は、毎日シャワーを浴びません。
1週間に1度ハマムという公衆浴場みたいなところで、体を綺麗に洗います。
お風呂はないのですが、スチームサウナのような所で、1週間分の垢を落とします。
最初、私はそれを知った時、何てことだ!と驚きました。
日本だと考えられない事ですよね。
で、よくよく観察をしたり話を聞いてたりすると、これが理解できるようになったのです。
イスラム教徒は一日5回のお祈りを欠かせません。1回1回のお祈りに必ず体を綺麗にします。
つまり、1日5回体を洗っているようなものなのです。
トイレは、紙ではなく、水で洗います。
変な話ですが、これが、私達日本人にはなかなか出来ない事ですが、紙よりも綺麗に保つ事が出来ます。そして、空気が乾燥しているので、ジメジメもしないので、体臭がある人もほとんどいません。
これを知っているのと知らないのでは大きな差があります。
ただ1週間お風呂に入らないモロッコ人、
もしくは1週間に1回しか入らなくても綺麗なモロッコ人となります。
表面を見るだけでは理解できません。
ものの見方の目線を少し変えるだけで全く違うものになってしまいます。
いかに、中に入って、知ることで、理解出来るかという事を学びました。
こんな感じで毎日驚きと感動の連続です。
それでは、また♪

いかがでしたか?蒲地さんが今回感じたことって、本当に私もそうだな~と思いました。
なにごとも見かけだけではわからないことも多いものですよね。
特に、途上国などで現地の人々と生活する上では、日本とまったく違う文化の中で生活していかねばなりません。
そんなとき、現地の人と同じように生活し、同じ視線に立って物を考えることはとても大切ですよね

蒲地さん、これから2年間日々いろいろな発見などがあると思います!またその発見などを皆さんに伝えてくださいね

2011年02月22日
セネガルの医療現場~派遣中の協力隊員からの報告~

今日は昨年3月にアフリカ・セネガルに派遣された看護師隊員の宇都宮真由子さんからのお便りをご紹介したいと思います

日本の医療と途上国の医療の違い、そして、宇都宮さんが困難はありつつも、現地の看護師とともに、国の発展、衛生状況の向上のために活躍されていることがとても良く伝わる内容です

ではでは、じっくりお読みください~

佐賀の皆さま、ボンジュール(こんにちは)!
「マイマ ハリス!!(お金ちょうだい)
マイマ カドー(なんかちょうだい)!!」
こんな言葉をかけられるのにも 慣れた セネガル 看護師隊員 宇都宮です。
日本ではありえない光景も、ここで半年以上も生活をすれば日常になってきました。
私の任地タンバクンダは、首都ダカールから内陸へ約460KM (車で8時間)。
セネガル人ですら「タンバクンダは、暑い 遠い 何もないから行きたくない」というような町です。
私は結構気に入っていますが・・・そんな町での活動を紹介します。
タンバクンダ州は妊産婦死亡率・乳幼児死亡率がセネガルの中でも高く、
住民の保健・予防に対する知識不足のため、更なる悪化を招いていると言われています。
そのため多くの医療隊員(JOCV)が派遣され、私も看護師の1人として
なんと診察代が大人200F(日本円で40円)子供100F(20円)という
地域住民に一番身近な保健ポスト(日本でいえば診療所レベル)で活動しています。
みなさん、「アフリカの医療者」と聞いてどんなイメージを浮かべますか?
私は、時間・ルールを守らない、なのに宗教絡みのことは正当化してくる、偉そうにして仕事をしないなどのイメージを持っていましたが、
実際一緒に活動してみてそんなことはなく、時間厳守・働きすぎで倒れてしまうのではないかと不安になるほどです。
同じ地球の片隅で働くそんな彼らの現状を今回皆様に伝えることができればと思います。


セネガルでは医師レベルのことを看護師がするので、保健ポスト長ももちろん看護師です。
保健ポストでは、診察・入院・妊産婦検診・分娩介助・予防接種・薬の販売・啓発活動と盛りだくさんのことを行っています。
これだけ多くのことを、看護師2人看護助手3名(無資格の助産師含む)で行っており
はっきり言って人員は足りず、隊員の私ですら医療行為以外のことも手伝っていて猫の手も借りたい状況です。
前任者が村で啓発活動を行なってくれたことで、地域住民の受診率は上がり、嬉しいことの反面
現段階では医療者を増やすことができない→医療サービスの質の低下→住民の受診率低下→診療所の収入低下
という悪循環を懸念しています。
そのため、少ない医療者の中で、いかに効率よく診療を進めるか?
無理・無駄・ムラを無くそうということを目標に挙げ、
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)も絡めてルールの徹底化を図っています。
具体的には、整理番号と共に受診チケットを販売することで、

チケットの買い忘れの防止(いままでは料金を忘れても、次回は払ってねというやさしい言葉で終わっていた)受診者の間での順番モメへの防止(もめることでその度に診療がストップしてしまう)など、
日本で当たり前にやっていることなのですが、こちらではまだされていないことでした。
他にもこうやったら、スムーズにできるのでは?というアドバイスを行い、小さいとこからコツコツと日々改善を行っています。
さて、根本的にこの地域で医療が遅れている理由には言語の多様化による情報・知識不足があると私は考えています。
公用語はフランス語及び現地語のウォロフ語なのですが、
タンバクンダでは多くの民族が混在しており、各言語も違い、この公用語が通用しない人も多くいます。
多くの看護師は、首都から派遣されているため、彼らの言語がわからず、地元人である看護助手に通訳に入ってもらい診察を行っている状態です。
そのため時間もかかりますし、患者さんにどこまで伝わっているのか?の確認が不十分に思えます。
これらの地方住民が日進月歩の医療の中で取り残されていっていることは、JOCV(協力隊員)としてどうにかできないものか?と日々悶々としています。
このような状況を改善するために視覚でわかりやすく分かるような絵などが啓発活動では使われているのでもっと医療に興味を持って貰えるように、私も視覚で訴えていけたらと思います。


また保健ポスト建物自体も老朽化が進み、屋根や床が崩れ始めています。


こちらも今後直していきたいと思っており、ハード面からもアプローチしていく予定です。
日本の病院とは考えなければならない視点が違い、
最初はここで何ができるのだろうか?と思っていましたが、
理解あるスタッフに支えてもらい、なんとか自分がしたいこと、やらないといけないことが見えきました。
世界の医療の格差を身をもって知った今、少しでも何か変わってくれればと活動あるのみです。
最後に「人は生まれる場所は選べない」
「だけど生きてく方法を選ぶ権利はあるし、お互い補って生きていくことはできる」
ことを信じて、この国の医療の発展に携わっていきたいと思います。

いかがでしたか?
「人は生まれる国は選ぶことはできない」
「しかし、補い合って生きていくことができる」
目には見えないけれども、私たちの身の回りの物はすべて海外と繋がっていること。
私たちは遠く離れたアフリカとも繋がっていることを忘れず、お互いが協力しあう世の中になるといいなと思います。
宇都宮さん、残り約1年、セネガルでの貴重な時間を身体に気をつけてお過ごしくださいね

セネガルの医療が少しでも発達することを願って…☆
2011年02月21日
ボリビアから
今日はボリビア派遣中の鶴田義久さん(平成21年度4次隊・野菜栽培)からお便りが届いていますので、ご報告します
鶴田さんはボリビアのサンファン市役所に配属され、野菜栽培の支援や地域での野菜の消費拡大のための栄養講座を開催したりしています。
それでは、ごゆっくりお読みください

日本の3倍の国土面積を持ち、スペインからの移民や原住民族、またその混血といった様々な人種を抱え、西は高地アンデス山脈地域、東は低地アマゾン川流域に属しひとつの国でありながら様々な顔を持つ国ボリビア。
最近になってウユニ塩原やエケコ人形が有名になったおかげで名前が売れてきた国です。

まだまだ多くの人がボリビアと聞いてどこにあるどのような国か想像がつかないと思いますが、豊かな資源に恵まれ、アンデスの古い歴史を持ち、広大な自然が広がるこの国は将来世界有数の国家となりうる底力を秘めています。
今はまだ黄金の玉座に座った乞食と揶揄されるほど貧しい国ですが、その素質は高く我が国日本としても強力な繋がりを持ちたい国だと言えるでしょう。
現在私はボリビアの人々の生活が良くなることにわずかでも協力できればと思い、この国で青年海外協力隊活動を行っています。
ボリビアと言えば荒涼なアンデスの大地に力強く生きる人々を想像なさるかもしれません。
たしかに人口はアンデスの高地に集中し、人々は富士山よりも高い寒冷な場所で生活を行っています。
ですが先に述べたようにボリビアの顔はそれだけではありません。むしろ国土の多くは低地アマゾン流域に属し、南国フルーツが豊かに実るほぼ常夏の亜熱帯気候となっています。私が活動を行っているサンタクルス県もそのような地域に属します。

高地アンデス地域は我々東アジア人よりやや色の濃い、しかし同じモンゴロイドであるケチュアやアイマラといった原住民族の方が数多く暮らしていますが、低地はカンバと呼ばれる欧州系との混血の人々が多く暮らしています。彼らカンバはまさにラテン系の人間で、音楽と踊りをこよなく愛す陽気でおおらかな人々です。

ボリビアで働く多くの人は貧しく、定職を持っている人でも一日の給料は日本の自給ほどにもなりません。
中にはびっくりするほどの金持ちもいますがそのような人はごくわずかで、私が指導を行っている農家の方々はほぼ自給自足生活を行い、ごくわずかの売上で生活用品を購入すると言ったぎりぎりの生活を行っています。
大学を出、公務員ともなれば月300ドル程の収入を得ることができますが、ほとんどの人は子供を大学に行かせる余裕もなく、公立の学校に通える子供たちでも授業は半日だけ。残りの半分は働いています。
この国での生活もそろそろ1年となり、もはや当たり前の光景になった働く子供達。
10歳にも満たない子供たちが当たり前のように働いているということは、日本では想像することしかできない当たり前ではない光景でした。
彼らは裕福を知りません。豊かさを知りません。
ですが、ひとりひとりのその顔はとても輝かしく、決して自分が不幸だとは思っていません。
今の日本を思えば生活の豊かさが必ずしも人生の豊かさとは言えないと思います。
貧しいながらも幸せであれば、それは素敵な人生であると言えます。
同じように、私の活動は人々の生活が豊かになる手伝いをすることであって、それが直接人々の人生の豊かさに繋がるとは限りません。ですが、その人々が私の活動を受け入れてくれる、喜んでくれる事が私自身の人生を豊かにしてくれます。
残り半分となったこの協力隊活動。
帰る頃には、人々の人生が豊かになる手伝いができたと言えるようになっているでしょうか。
いかがでしたか?
物資があることが人生の豊かさではなく、村のみんなが喜んでくれること、それ自体が自分が幸せだと思う鶴田さんは、本当に素敵な協力隊活動をされているんだなと思います

残り1年の活動頑張ってくださいねっ


2011年02月21日
ブルキナベの面白エピソード☆
テーマは「ブルキナベ(ブルキナファソ人のことをこう呼びます)の面白エピソード
 」
」ではではごゆっくりお読みください

【美しい国ブルキナ(古い)】
美しいです。ブルキナベ。
…特に姿勢が。背中がしゃんとして、りりしくもあります。
猫背のおいらから見れば、羨しすぎるスタイルです。特に女性がですね。
その理由のひとつは、物を運ぶ時に頭にカゴを乗せて運ぶからです。
時には、なんでそんな大っきなものも?!というくらいのものもヒョイと頭に乗せて運んじゃいます。
この運搬作業で重要なことは「力」ではなく、「バランス」です。
背筋と腹筋を活用して、身体全体のバランスをとります。
でなければ、あんな大きな荷物を頭に乗せて運べません。
だから、ブルキナベの女性(一部のひとを除いて)は腹筋と背筋が、みごとに発達しており美しいスタイルをキープできています。
ああ、羨ましい。 by猫背。
お母さんレベルになると、赤ちゃんをおんぶしながら、頭にカゴを乗せてスタスタ歩くことができます。
その状態で、草むらの中で立ったまま小用を足している姿を見かけると思わず「あっ晴れ」と叫びたくなります。
でも、たっしょんはいけませんよ(*^_^*) by保健系隊員
ここで一句、
「環境も こころも美しくあれ ブルキナベ」
【踊るブルキナベ。とりあえず、踊っとけ!】
こちらの人々は基本的にジャッキー・チェンが好きです。
ブルキナファソで一番、クールなのはカンフーです。
学校でバスケを教えようとしても、空手を教えてくれと言ってきます。
初対面の人は、決まって「とりあえず空手はできるのか?」と聞いてきます。
そんな時、自分は「相撲ならできる。」と答えて、ついでに相撲の四股(しこ)の踏み方を教えてあげます。
しかし、そんな時ブルキナベは何を勘違いしたのか必ず腰を振って踊りだします。
その姿は大変こっけいであり、微笑ましくもあり、…アホっぽいです。
バスケのシュートを教える時も、「膝を曲げて、身体全体でシュートを打つ」って教えたら、やっぱり腰振っていました…。
アン・ドゥー・トロワ♪…って。
バナナ売りのおばちゃんも、通りかかった店の音楽に合わせて、腰振っていました…。
頭のカゴにバナナを乗せたまま。アン・ドゥー・トロワ♪…って。
ブルキナベは「踊る」というDNAがすでに備わっている感じです。
本当にみんな、踊ることが好きな国民です。
いかがでしたか?
これまで3回の投稿を通じて、ブルキナファソの国民性・文化が少しでも伝わったでしょうか><?
協力隊員は、日本と全く違う文化・習慣の中、それぞれの活動を繰り広げていかねばなりません。でも、その中で、大切なものはなにか気付き、経験し、きっと、日本に戻るころには身体も心も人一倍大きくなってくることでしょう。
本村さん、ブルキナベに負けず、頑張ってくださいね~
2011年02月18日
ブルキナの食事情(虫が苦手なら見ない方がいいかも!?)
協力隊員はこんなもの食べています。
でも、虫が苦手な人は決して見ないでくださいね…。
先輩宅で出された毛虫のスープです。自分は今だ食べられません。

ちょっと、シャレたレストランで食べた鳥肉料理です。もちろん素手で食べます。

ブルキナベの主食トウです。材料は穀物で、ソースをつけて食べます。美味い!

トウを作ってみました。このかき混ぜの過程が重要で、出来を左右します。


つづく
2011年02月14日
女性が元気なブルキナファソ
今日はアフリカ・ブルキナファソより、昨年6月に出発した本村大輔さん(H22年度1次隊・看護師)からのお便りを紹介します

本村さんはディエブグ保健行政局で青年海外協力隊・看護師として活躍されています

これから数回に分けて、本村さんからのお便りをご紹介したいと思います^^
本村さんが見たブルキナファソの女性の姿とは?
ではではごゆっくりお読みくださ~い

ブルキナファソでは、女性の社会的地位や教育レベルが低いこと等、ジェンダ―に関する問題は今なお根強く残っております。
地方の村落部に行けば、看護師隊員ながら、なおさらそう思います。
しかし、ブルキナのオバちゃん達は強いですよ。
八百屋のオバちゃん軍団なんか最強で、ギャングかと思わせるほどの攻撃力を持ち合わせています。
うっかり、目を合わせてしまったりしたら最後、何か野菜か果物を買うまで、腕を掴んで離しません。
大阪のおばちゃん顔負けの力強さで逆バーゲンセールです。
同期隊員の乙メン約2名が、オバちゃんに腕を引っ張られつつ、店の中に連れ込まれている光景は、「あな恐ろしや…」と思いました。(そして、あまりにも恐ろしくて助けに行かないオレ。)
また近所の雑貨屋では、オジさんの店番の時は値切りに応じてくれたり、とても親切にしてくれます。
しかし、オバちゃんの店番の時は最悪。ビタ一文、安くしてくれません。
「10000Fcfa(日本円換算;2000円)なら10000Fcfa!嫌だったら、よそに行け!!」と言われます。
こちらの要求には一切応じないため、昼休み明けに店当番がオバちゃんからオジさんに変わったことを確認して、また店に行くという健気な努力(せこい?)をしています。
なんとか生活費の節約をするためです(涙)
この前は、混雑している高速バスの席の隣で、かっぷくのいいマダムが席ふたり分取って平然と座っていました。
このマダムの肉圧に圧迫され続けた首都までの4時間半のバスの旅…、暑苦しかった(T_T)
そんな訳で、なんとなく自分の頭の中ではブルキナ女子>ブルキナ男子のイメージができちゃってます。
自分の職場でも、男性職員より助産師や女性看護師が強いです。絶対に勤務交代なんかできません。
そんなこと言ったが最後、待っているの死より辛い「吊るしあげ」です。「あな恐ろしや…」
こんな素敵なマダム(大人の女性を尊敬して呼ぶ語)達が沢山いらっしゃるブルキナファソ。
マダムを敵につけるか、味方にするかでこれからの協力隊活動の結果が大きく左右されるのは、言うまでもありません。
しかし、彼女ら強い女性がいるから、ブルキナファソ社会は活気があるのだなとも感じざるを得ません。
女性が元気な国は、きっと栄える!(byもののけ姫のアシタカより)
合掌。
そこで、女性が強い訳を考えてみました。
その① 金銭的に余裕が無いため
ブルキナベ男子は家をほったらかしにして外に遊びに行き、家に金を入れない旦那がいるとしばしば聞きます。(全ての男性がそうではないですが)
そんな旦那を頼りにせず、自分で商売をして子供を養っている肝っ玉お母さんをよく見かけます。
後から思えば、金銭的にもシビアなことは、自分と自分の子供たちの食いぶちがかかっているからだということですね。
その② 社会的立場の余裕が無いため
途上国では珍しくないことですが、ブルキナファソでも、まだまだ女性の地位は低いし、就学率も低いです。
女児は小学校に通えず、家の手伝いをさせられることもしばしばあります。
結局、社会に出ても、偉くなるのは、男だろうという親の考えもあると思います。
現状がそうなので、親の気持ちも分からなくもないですが、教育費をなかなか捻出できないという現状もあると思います。
その③ かわいい子供のため
前述したダメダメな亭主であれば、残された子供を守るのは自分しかいないという思いからでしょうか、そのため、女性たちはさらに精神的にも強靭になるのでしょう。
守るべきものがあるということは、人を強くさせますね。
たくましい女性は好感が持てます。素敵だと思います。
つづく
2011年02月07日
ニカラグアからボランティア活動紹介!
みなさん、こんにちは
今日は、なんと、日本の裏側、中南米ニカラグアから、佐賀市在住の山下優子さんからのお便り が届いているのでご紹介します
が届いているのでご紹介します
山下さんはニカラグアのジョン・F・ケネディ小学校に小学校教諭として昨年6月に派遣されました。
派遣されて半年経つ今、ニカラグアではどんな活動をされているのでしょうか!?
ではごゆっくりお読みください~
佐賀県の皆さん、こんにちは。
青年海外協力隊22年度1次隊の山下優子と申します。
現在、私はニカラグア共和国という国で小学校教諭として活動をしています。
ニカラグアは中米のほぼ真ん中に位置し、北西はホンジュラス、南はコスタリカと国境を接し、東はカリブ海、南西は太平洋に面しています。人口は5,743,000人(2008年度)で、全土が熱帯性の気候に属しています。季節は2つに分かれ、雨季が5月から10月、乾季が11月から4月です。


私の任地は、首都のマナグアからバスで1時間半程行ったレオン県レオン市(太平洋側)という所です。
レオン市は、第2の都市であり、1851年まで、200年以上の間ニカラグアの首都でもありました。
中心にある公園には中米最大のカテドラル(=大聖堂)があります。
余談ですが、レオンとはライオンという意味で、いたるところにライオンの像があります。
もちろんカテドラル内外にもライオンの像はあります。

また、郊外には世界遺産にも登録されているレオン・ビエホ(=火山の噴火によって廃墟となったスペイン人によって作られた植民地都市の遺跡)もあります。
私は、ニカラグア人の家庭にホームステイしながら楽しく生活しています。

私のニカラグアでの生活は7ヶ月がたちました。
配属先のジョン・F・ケネディー小学校では、主に算数の授業を主体に協力活動を行っています。
毎日、大好きな子どもたちからたくさんの元気をもらっています!!
そして、1日1日が過ぎるのが大変早く感じます。

11月には、エルサルバドルで行われた算数の中米地域研修会に同僚の教師と一緒に参加し、この経験を踏まえ、私の学校で教師たちに算数の教材・教具の研修会を行いました。

ニカラグアの大きな社会問題の一つに、13~15歳の妊娠率が非常に高いという問題があります。
そこで私は「何ができるのだろうか?」と考え、卒業していく6年生に対し、助産師隊員と共同で性教育の授業をしました。
この国では、小学校でも留年制度があり6年生とはいっても15・16歳の子もいます。
そのため、次回は性感染症も兼ねて授業を行いたいです。

今後は、配属先の小学校や近隣の小学校の教員に対し多くの算数研修会を行って行きたいです。
それから、町のいたるところにゴミが落ちているのでゴミ拾い運動を地域住民と行いたいと思います。
それに合わせて、同校の授業でも環境授業も行いたいとも考えています。
それから、ニカラグア内で催した日本文化紹介の中で書吟(書道のパフォーマンス)もしました。
ニカラグアでも、私の大好きな書道を紹介することができて大変嬉しかったです!!
また、私は幼い頃から書道を学んでおり佐賀北高等学校芸術コース書道科で本格的に書道を学び、大学・大学院は佐賀大学で書写・書道の研究をしてきました。
「書道家」山下優雲としても書道の楽しさをニカラグアに広めていきたいです。


ここで、少し食べ物の紹介をしたいと思います。
ニカラグア人は、ガジョピントという豆ごはんをよく食べます。
日本でいう赤飯のようなごはんです。
作り方は、白米と豆と玉葱やピーマン、にんにく等を油・水・塩で炊き込みます。
ニカラグアでは、普通のごはん(=日本でいう白いごはん)も野菜・油・水・塩と一緒に炊き込みます。かなり油っこいです。
ニカラグア人は朝と夜はパン等で軽く済ませ(人によっては夜は食べません)。
昼に、ごはんや肉等をしっかり食べます。
写真は、ある日の食事風景です。ガジョピント・チーズをかけた挽肉の卵とじ(とうもろこし粉のトルテージャ入り)・アボガドサラダです。手作りジュースは、ハマイカジュースといって花のジュースです。

最後に、ニカラグアの伝統衣装を着た子どもたちです。

いかがでしたか?
子ども達、カワイイですよね~
約半年が過ぎて、少しずつ軌道に乗っている様子がうかがえました。
その分問題もたくさん見えてきて、でも、思い通りにいかなかったり…色々と、悩み、ぶつかることも多いのではないかと思います
ほんと、体調には気をつけて、引き続き活動がんばってくださいね !
!
応援しています

2011年01月18日
☆報告☆地球発見隊!有明南小学校
寒い日々が続きますね~


この寒さ、どこまで続くんだろうー…空もどんよりした日々が続きますしね 早くあったかくなってほしいものです><
早くあったかくなってほしいものです><
さて!今日はそんな寒さにも負けず、昨年9月に帰国した有田町出身の深海さんによる地球発見隊が1月17日(月)に行われました~
有明南小学校はのどかな山の上にある小学校です。緑に囲まれた小学校で、寒さにもまけず、半袖短パンの元気な子ども達ばかりでした
今回の講師は昨年9月に帰国したばかりの協力隊員OGの深海さん。
小学校3年生を対象として、任地であるタイについてお話ししてくれました。
小学3年生にとっては2時間という、とても長い時間だったのですが、子どもたちはそんな時間なんて気にしないくらい深海さんの講座に聞き入っていました
子どもたちが一番びっくりしていたのが、タイの食文化!
「白いイモムシを食べること、イモリを食べること」
海外の人にとっては日本人が生の魚を食べることが、外国の人にとって衝撃的なことだそうです。
どこの文化も生まれ育った習慣や文化の中、それはその国の人にとって当たり前になっていて、190以上も国がある中それぞれの文化があって当然。
有明南小学校のみんなは異文化を知って、驚き、また、日本もそうなのか、と納得していました
また、タイの挨拶の仕方や曜日によって変わる制服などなど・・・たくさんのことを知ることができました。
地球発見隊は佐賀県の青年海外協力隊を地域の小中学校に派遣する事業です
子どもたちにとって、広い世界へ目を向けるよいきっかけとなること間違いなしです!
もし興味がある、という方はまた来年度も実施予定なので申し込んでくださいね
(そのほかにもJICAの出前講座もいつでも受付中ですよ!!)

「タイってどこにあるの?」
みんなはまだ世界地図は習っていないのに、一生懸命答えてくれました!


最後はタイのおどり方を学んで、みんなで踊りました~
2010年12月02日
エチオピアと仁比山小学校のテレビ電話交流!


久冨さんは、H22年3月にエチオピアに向けて日本を出発し、村落開発普及員として、オロミア州メキ・バツ農業協同組合に赴任しています。
久冨さんの任地であるエチオピアは首都アディスアベバから車で約3時間にある小規模の街。
水道も電気も不安定で、停電は毎日のように起こり、それに伴って水道の利用もできなくなります。こういった問題もある中で、久冨さんは現地の人たちに支えてもらいながら、現在活動を行っています。
久冨さんの活動は、主に、ファイナンスの面でのアドバイスを中心とした組合や村落の活性化のための活動を行っています。
今回、久冨さんの出身校である神埼市仁比山小学校からの強い希望もあり、この企画がスタートしました。
対象となった仁比山小学校4年生は11月10日にもネットでの交流を行い、学びを深めてきました。
そして、今回、久冨さんから届いたビデオレターを見て、日本とエチオピアの違いや共通点などを久冨さんと話し合いました。
写真で見てわかるように、久冨さんの後ろはエチオピア、アフリカの広大な大地です


エチオピアにはサッカーボールがないこと、文房具もシャープペンや鉛筆はなく、ボールペンだけであること、定規も持っている子どもは少ない、などを知り、子どもたちは日本との違いに驚いていました

下の写真は、久冨さんが質問に答えたことに熱心にメモをする児童達です。
なかなかこういった授業は受けることができないと思うので、みんないい体験してるなぁと感じました

まとめの感想では、「途上国へ行こうと思ったきっかけなどをきいて、久冨さんの思いが伝わり、心が揺さぶられた」と、小学生4年生でこんなコメントがでるの!?と驚くような発表をしてくれた子もいました。
きっと、この子どもたちの中には、大人になっても、久冨さんと通じたこの授業を覚えてくれている子がいるんだろうな、と思いました。
佐賀県でもこういった国際理解講座が浸透していき、佐賀の子ども達が世界へ目をむけるきっかけづくりとなればいいなと感じた交流でした

上の写真は11月10日のエチオピアとの交流で気付いたことを子どもたちがまとめました!
2010年10月06日
H22年度2次隊が出発しました!
寒い~![]()

めっきり寒くなってきましたねー ほんと、季節の移り変わりってはやいですよね!この前まで暑かったのに、今朝なんて冬のような寒さでした
ほんと、季節の移り変わりってはやいですよね!この前まで暑かったのに、今朝なんて冬のような寒さでした
私は寒さが大の苦手なのでこれから朝起きるのがつらくなりそうです~
さて、話は変わって、先月9月16日に県庁表敬訪問を終えたH22年度2次隊が9月4日までに全員無事出発しました!
出発した隊員はシニア海外ボランティア〈40〰69歳)が3名、青年海外協力隊(20〰39歳)2名の計5名です。
派遣国、職種は以下のとおり
〈シニア海外ボランティア〉
・佐賀市出身 エクアドル派遣 職種:土壌改善
・佐賀市出身 フィジー派遣 職種:漁業技術教育
・伊万里市出身 パラグアイ派遣 職種:電気
〈青年海外協力隊〉
・唐津市出身 セネガル 職種:小学校教諭
・有田町出身 モロッコ 職種:村落開発普及員
今回の特徴として、いつになくシニアボランティアの占める人数が多い!
佐賀県のシニアが元気なのは非常に喜ばしいことですよね
今回派遣されたシニアボランティアの中には、「退職後、このまま家でボーっとしていたら病気になりそうだと思った」と話される方もいて、退職後の生きがいを求めて、これまでの経験をいかそうと参加を決意されたそうです
また、今回が派遣5回目!という驚きの方も 今回は初めての奥さんとお子さんをつれての派遣だそうです!
今回は初めての奥さんとお子さんをつれての派遣だそうです!
どうしてそんなに何度もチャレンジして行くのか?と聞くと、2年間の活動を終えて、共に働いた職場の同僚たちから涙ながらに感謝され、惜しまれて去るというシーンが忘れられないからだそうです
みなさん、ほんとに家族や親しい友人と離れてでも、途上国の人々の役に立ちたい!というそれぞれの熱い想いを胸に、出発されていました
みなさんの現地での活躍を佐賀から応援しています
そして、2年後無事に佐賀へ帰ってきてくださいね~ いってらっしゃーい
いってらっしゃーい
2010年09月29日
インドネシアだより

今日はそんな寒さしらずのインドネシアからお便りが届いています

太良町出身の野田暁子さん、ちょうど派遣されて1年とちょっと経過しましたが、どんな土地で、どんな活動をしているのでしょうか?
子どもたちの写真もとってもかわいらしいです
 それではお読みください
それではお読みください

佐賀の皆様、初めまして。
私は、去年の6月にインドネシアに派遣され、理数科教師として活動しています。
インドネシアは1万8千以上もの島から構成される島国であり、人口は日本の約2倍、土地面積は約5倍になります。
その人口の6割が集中しているというジャワ島に私は住んでいます。
公用語はインドネシア語。私の任地ではジャワ語が地域の言葉として根付いています。
活動先は、ジョグジャカルタ特別州の南に位置するイモギリ第一中学校です。
生徒数約650人、教職員数約50人、うち理科教員6人、数学教員4人で、インドネシアでは普通規模の学校です。ジョグジャカルタはボロブドゥールやプランバナンといった世界遺産で有名な所でもありますが、イモギリは、有名な王家のお墓がいくつかあり、神聖な場所といった感じでしょうか。ジョグジャカルタ市内から、バスを乗り継いで1時間半くらいで行くことができます。
イモギリの町は、田んぼが広がり、人々も穏やか。
私ののんびりした性格にあったところです。
2006年の中部ジャワ地震の時、被害が大きかった地域で、任地の学校の再建も含め日本の無償資金援助やボランティアが入った所であり、人々はとても親日的です。
また、終戦前に日本の統治下にあったインドネシア。イモギリのこの地にも、日本軍が入ったらしく、お年寄りと話す時は、よくこの話題がでます。少し日本語を覚えている人も。
下の写真はイギモリの朝の風景です。

近所のいたずら好きの子どもたち!かわいい!

さて、活動内容です。
職種は理数科教師で、主に理科教育に携わっています。
理科の先生と一緒に理科の授業改善、実験室の整備、地区勉強会への参加と助言などを行っています。新規の派遣でしたので、最初は私も任地先の先生方も、協力隊の存在に何をしたらよいのかとまどい、活動がはっきりしない時期がありました。
私はとにかく、インドネシアの理科教育の現状と問題点の把握に努めることにしました。
ここイモギリ第一中学校は、イモギリ地区のリードとなるモデル校。他の学校よりは教室や実験器具も揃っています。しかし、その利用や教育方法は残念ながらまだ十分ではないように感じます。私自身のものさしで測るのではなく、現地の色んな先生方の意見を聞きながら、理科教育の改善に努めていこうと思うようになりました。
現在は、担当の理科の先生(カウンターパート)の授業を半分ずつ受け持ち、理科の授業がどうしたら良くなるか、相談したりお互いに学び合うような形をとって活動しています。インドネシアの子どもたちに合う教育を考え、試行錯誤しながら、理科を教えています。
下の写真はカウンターパートの授業です。机間巡視をし、生徒の様子を見ている様子です。

授業の一場面;水圧の性質を調べる実験の説明中

インドネシア人の約9割はイスラム教徒です。
任地先でもほとんどの生徒はイスラム教徒。学校のスケジュールもイスラムの行事に左右されます。
朝は7時から授業開始。1,2,3,4時限目を連続して受け、その後の休み時間はお祈りします。また5,6,7時限目の授業を受けると、また休み時間はお祈りの時間。忙しい子供たち。それでも、元気に無邪気に授業に参加する子供たち。かわいくてしかたがありません。(最後の授業8限目はさすがに疲れ気味ですが…)
最近の授業で気づいたことがありました。「ここの部屋の温度は平均何度くらいか知ってる?」と聞いたところ、子供たちは「10度!」「20度!」「30度!」などと、答えはバラバラ。「平均32-33度くらいだよ」というと、初めて知ったようでした。インドネシアの気候は一年中暑いです。天気も晴れか雨。天気予報こそあれ、ほとんど見ないようです。温度の感覚、天候の変化には、関心がうすい子ども達。しかし、日本の「雪」には異常に関心を示します。また、0度以下の気候もある、すなわち普通の水が凍るぐらいの気温が実際にあることにも、大変驚いているようでした。数字は知っているけど、それが自然の現象をイメージすることつながってないのですね。
こういう授業のやりとりから初めて知る、インドネシア人の感覚や小学生からの予備知識も多いです。子供達のことばもよく聞いて、どこからでも常に学ぶ姿勢を持ち、楽しく活動していきたいと思います。

授業の一場面;水の増減から石の体積を求める実験。単純な実験だけど、よく話し合う子どもたち
2010年09月15日
スリランカだより


今日は、今年の6月にスリランカへ派遣された、武雄市出身の一ノ瀬加代子さんからのお便りを紹介したいと思います

私はスリランカと言えば、カレーとお茶!あと、首都の名前がめちゃくちゃ長い!というイメージがあります。
でも、ここは長年タミルとシンハラの民族紛争が続いていた国ですよね。協力隊活動する上では、そういった面でもいまだに大変なこともあるだろうと思います

そんな国、スリランカからのお便りです

佐賀の皆さん、こんにちは!
私はスリランカで村落開発普及員として働いています。
赴任して1年と2ヶ月。あっという間に時が過ぎ、残りの10ヶ月もあっという間に過ぎるのかと思うと焦りと不安でいっぱいです。
今日はいつも私を怒らせ、失望させ、そして笑わせてくれる楽しいゆかいなスリランカの仲間たちを紹介します。
私はJICAの円借款で行われる予定のキャンディー市下水道事業に携わっています。
私はその下水道事業の対象地域である低所得地域2箇所で、地域の問題であるトイレの汚物のオーバーフローの問題、道路や溝にポイ捨てされるゴミの問題に中心に取り組み、更に子どもたちに英語教室を開き、英語の学習を通してマナーやよい習慣などを教えたり、更に公園に行って遊んだり、お菓子作りをしたりと健全な子どもの育成に取り組んでいます(と、かっこよく言ってみました)。
今日紹介するゆかいな仲間たちは、私が働く低所得地域の「子ども」です。
英語教室を始めて早7ヶ月。母親たちからの要望により教室を始めたのですが、始めた当初は、とても大人しい子どもたちでした。じっと口を結び、しっかりと勉強する子どもたちでした。

英語を教えるのはスリランカ人4名。私はコーディネーターです。
先生が不在の時には私が教えます。また時にはネイティブを招いての教室など色々な催しを行っています。

それが段々慣れてくると…ちょっとでも隙があると一瞬にして、THE カオス!!
ぎゃーぎゃーぴーぴー!!ここは動物園ですか~!!!!????と叫びたくなる程、実際叫んでますが(苦笑)、喧嘩を始める、関係のない話を始める、歌い始める、そして走り回り始めるのです。。。本当に頭が痛くなります!

何をやっているのやら・・・授業中ですぞ・・・!!!
もう無理!!と何度もくじけそうになりましたが、それでも子どもはかわいくて無邪気で、私を元気にしてくれるのも子どもたちです。
あと10ヶ月一緒に楽しいひと時を過ごせたらなあと思います。
そしてこの地域は、イギリスの植民地時代に、キャンディー市役所の労働者として連れてこられたカーストの低い人たちが住んでおり、様々な問題が原因で他の地域からの差別などがありますが、この子どもたちが将来、自分たちの地域を誇りのあるコミュニティーに変えていってくれるといいなあと願っています。
下は子どもや住民とたわむれている様子。




2010年09月08日
ソロモンだより

申し訳ありません

私は一応、保健師なのですが、人の体調管理には厳しいくせに自分の体調管理には甘いのがいけないトコですね

さてさて、今日はソロモンに派遣された青年海外協力隊、看護師の光武章子(みつたけあきこ)さんからのお便りです


光武さんは白石町出身で、2009年の1月に出発されたので1年半がすでに経過し残すところ、あと数カ月の活動です。
私も似たような活動をしていたので、なんだか読んでいてほんとにそうだなぁと、光武さんの思いに感動してしまいました。
ではでは、じっくりお読みください

こんにちは。
私は今ソロモンの首都、ホニアラから少し離れたところにあるマララクリニックで現地の看護師たちと一緒に患者さんの看護をしています。
ここはホニアラ市外の5つのクリニックと、27の村、そして6つの学校を管轄しているクリニックで、毎日多くの患者さん達が、ここを訪れます。
クリニックでの主な活動内容は、外来診療・妊婦検診・乳児検診・6つの村への巡回医療・学校訪問などです。
日本と違ってここは医師がいないので、医師が普段している診断・薬の処方・その他全てのことを看護師たちがしています。
私はソロモンに来るまで、途上国の医療をテレビや本などでなんとなくイメージできる程度しか理解していませんでした。なのに自分は分かっているつもりでいました。
しかし、実際にソロモンの医療を目の当たりにし、自分がいかにそれを理解できていなっかったかをとても痛感しました。
日本であれば必ず助かる患者さんが少しずつ悪化し、最期を自宅で迎えるために家に帰る患者さん。
限られた医療器材の中で患者さんたちを診て、診断・薬の処方をする同僚たち。度々薬その他の物品の在庫がなくなるクリニックの現状。それでも看護師たちが限られた中で、私たちが思いつきもしない知恵を出し、上手にその不足分をカバーしているのを見て、いつも感心させられています。
今まで自分がやって来ていた看護は、物が全て揃っている日本だからできたんだな、と、心から思いました。
ここソロモンで、本当に多くのことが学べ、多くのことに気づかされます。
そんな中で、自分が外国人として、現地の看護師たちと一緒に仕事をする難しさも感じました。
ソロモン人にとって、日本はとても大きな国であり、大きな病院がたくさんあって、医療レベルも高いというイメージを持っています。しかし、ソロモンの看護師たちもしっかりとしたプライドを持っていて、そんな看護師たちを患者さんたちはとても頼りにしてクリニックを訪れます。
そんな中に自分が、看護師として来て初めのころは、私を「日本人」としてしか見てもらえませんでした。
同僚たちとの間に距離を感じ、どうしたら日本人としてではなく、私を同じスタッフとして受け入れてもらえるだろうか、と、とても悩みました。
けれど日が経つにつれ、ふと「クリニックでの活動はとても楽しい」と言っている自分に違和感を感じるようになりました。
日本の医療が進んでいる、と思っているソロモンの看護師たちにとってこの言葉は、決して良い言葉ではないな、ということに気づいたからです。
それ以来、そのような言葉ではなく、みんなとの距離をなくしたい、ということを分かってもらうために、みんなが私に頼みたいことがあっても、言いづらそうにしている時に、自分から動くなど、みんなが私に気を使わないように行動し続けました。
そして今、同僚たちはみんな私をニックネームで呼び、時々みんなと一緒にソロモン式で昼食を取ったりしています。
そのソロモン式で最初、とても戸惑ったのが「手を使って食べる」でした。ソロモンではこれが習慣の一つであり、外で食事をするときはリーフを皿代わりにします。ソロモンの人たちは、自分たちが釣ってきた魚・貝、そしてニワトリなどをさばいて、道端でよくバーベキューをしますが、それを道行く人は買い、その場で話をしながら食べます。クリニックの近くでもその光景をよく目にしていますが、ときにはその中に自分も入り、みんなと一緒に手で食べたりしています。
ソロモンに来て1年と8カ月が過ぎ、これまでいろんな経験をしてきました。それは決して楽しい経験ばかりではありません。けれどつらい経験であればある程、そこから気づくことは、どんなに楽しい経験よりも素晴らしく、とても偉大です。
なぜなら、多くの困難に正面から向き合い続けるからです。ときにはそんな困難に負けそうになる時もあります。そんなとき、私は現地の人たちの小さなやさしさに、いつも心救われてきました。
でもそれは、日本にいたら絶対に気づかない程小さなものです。しかし、これまでそんな小さなやさしさが、とても大きな幸せとなって、私をいつも奮い立たせてくれました。ソロモンで経験した事全てが私の宝となっています。
私は看護師としてソロモンに来れて本当によかったと思っています。残り4カ月を切りましたが、悔いの残らないようにここソロモンで精一杯看護をしようと思います。